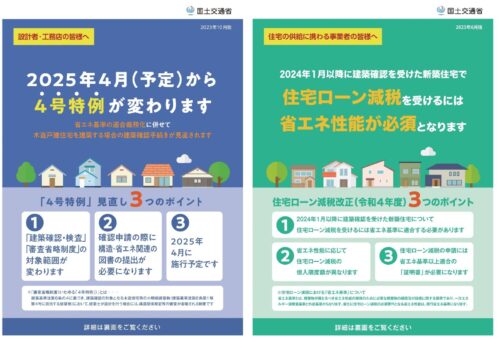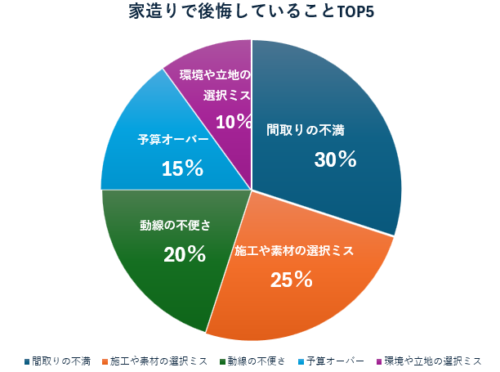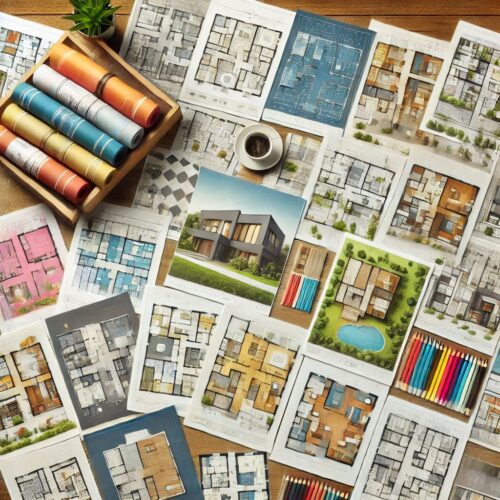土地が無いけど家を建てる費用は?3階建てでマイホームを実現する方法
2025年03月26日

「自分の土地を持っていないけど家を建てたい」「3階建て住宅を検討している」という方に向けて、土地が無い場合でもマイホームを実現する方法を詳しく解説します。本記事では、親族や知人の土地活用、借地の利用、自治体の支援制度などの選択肢を紹介するとともに、3階建て住宅のメリット・デメリットや建築費用の相場、コストダウンの工夫についても解説します。さらに、住宅ローンや補助金を活用した資金計画についても触れています。
目次
土地が無い場合に家を建てる方法とは
「マイホームを建てたいけれど、土地を持っていない」とお悩みの方も多いでしょう。しかし、土地が無くても家を建てる方法はいくつかあります。ここでは、土地を購入せずに家を建てる選択肢について詳しく解説します。土地取得のコストを抑えながら理想の住まいを実現する方法を見ていきましょう。
親族や知人の土地を活用する
親や親族、知人が所有している土地を活用することで、土地取得費用を大幅に抑えることが可能です。以下にその方法を紹介します。
| 活用方法 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 親から土地を譲り受ける | 親から無償または低価格で土地を譲ってもらう | 土地代が不要、住み慣れた地域に住める | 贈与税・相続税の対策が必要 |
| 土地を借りる | 親族や知人から土地を貸してもらう | 購入費不要、住宅ローンに集中できる | 契約条件を明確にする |
| 共有名義で購入 | 親族と共同で土地を購入し、その上に住宅を建てる | コスト分担が可能 | 名義トラブルに注意 |
借地を利用して家を建てる
土地を購入せずに住まいを持つ方法として「借地」という選択肢があります。これは、土地を所有するのではなく、借りた土地の上に住宅を建てる形態です。
借地権の種類と特徴
日本における借地には主に以下の2種類があります。
| 借地の種類 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 普通借地権 | 契約期間30年以上、更新可能 | 長期的に安定した住まいを確保 | 契約の更新料が発生する場合がある |
| 定期借地権 | 契約期間50年以上、更新不可 | 土地購入コスト不要、比較的安く利用できる | 契約満了時に住宅を取り壊す必要がある |
自治体の土地提供制度を活用する
自治体によっては、安価に利用できる土地の提供制度を設けている場合があります。特に、地域の定住促進を目的とした制度があり、活用すれば新築住宅のコストを抑えられます。
自治体が提供する主な制度
| 制度名 | 概要 | 対象者 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 定住促進住宅用地提供事業 | 自治体が安価で土地を貸し出す | 自治体が指定する条件を満たす家庭 | 土地取得費が低額 | 転売不可、一定期間の定住義務 |
| 空き家・空き地活用制度 | 自治体が空き地を活用する住居建設を支援 | 地域移住者など | 格安で土地を取得可能 | 自治体や地域の条件を満たす必要 |
土地付きの建売住宅を検討する
土地が無い状態で家を手に入れる方法として、「土地付きの建売住宅」を購入するという選択肢があります。
建売住宅とは?
建売住宅とは、不動産会社やハウスメーカーが土地と建物をセットで販売する住宅のことです。
建売住宅を選ぶメリット
- 土地の取得と住宅の建築がセットなので手間が少ない
- 購入価格が明確で住宅ローンの計画を立てやすい
- すぐに入居できる物件が多い
建売住宅のデメリットと注意点
- 間取りや設備が固定されており、自由な設計ができない
- 人気のエリアでは競争が激しく早く売れてしまう
- 細かいカスタマイズをしたい場合は注文住宅より不向き
建売住宅は選択肢の一つとして便利ですが、立地や設備が希望に合うか慎重に検討することが重要です。

3階建ての住宅を建てるメリットとデメリット
3階建て住宅のメリット
狭い土地でも十分な居住スペースを確保
都市部では土地の価格が高騰しているため、広い土地を確保するのが難しい場合があります。しかし、3階建ての住宅であれば、敷地面積を有効に活用しながら、延べ床面積を広く確保できます。例えば、30坪の敷地に2階建てを建てる場合と、同じ敷地に3階建てを建てる場合を比較すると、1フロアあたりの面積は減りますが、3層に分けることで必要な居住空間を確保できます。
都市部での有効活用が可能
都市部では、住宅密集地が多く、土地の区画も狭小化する傾向にあります。3階建てであれば、限られた面積でも十分な間取りを実現できるため、都市部での住宅事情に適した選択肢となります。また、1階部分を駐車スペースや店舗として活用するなど、土地を有効に使う工夫も可能です。
眺望や採光を確保しやすい
3階建ての住宅では、より高い位置からの眺望を楽しむことができます。特に、周囲の建物が低いエリアでは、3階部分にリビングやバルコニーを配置することで、開放的な空間を実現できるでしょう。また、上層階ほど他の建物の影響を受けにくく、採光の確保にも有利となります。屋上をバルコニーやルーフガーデンとして活用することで、さらに住環境を向上させることができます。
3階建て住宅のデメリット
建築コストが高くなりがち
3階建て住宅は、2階建て住宅と比べて建築コストが高くなる傾向にあります。理由としては、以下の要因が挙げられます。
| コスト要因 | 理由 |
|---|---|
| 構造の強化 | 3階建ては重心が高くなるため、耐震性を確保するための補強が必要になる。 |
| 基礎工事の強化 | 重量が増すため、地盤改良や基礎の強化が必要になることが多い。 |
| 設備コストの増加 | 配管や電気配線が長くなることで、工事費用が高くなる可能性がある。 |
これらの要因により、かかる費用は2階建て住宅よりも高額になりやすい点を考慮する必要があります。
階段移動の負担が大きい
3階建て住宅では、階段を利用する頻度が増えるため、日常の移動負担が大きくなります。特に、高齢者や小さな子どもがいる家庭では、上下移動の負担が暮らしやすさに影響を与える可能性があります。
この問題を緩和するために、以下のような対策を検討することができます。
- 老後を見据えた場合は、エレベーターの設置を検討する。
- 1階部分に主要な生活空間(リビング・キッチン・浴室)を配置し、寝室のみを上層階に置く。
- 階段を緩やかな勾配にして昇降を楽にする。
耐震性や構造計算が重要になる
建物が高くなるほど、耐震設計の重要性が増します。特に日本は地震が多い国であるため、3階建て住宅を建築する際には、次の点を考慮する必要があります。
- 法律に基づいた構造計算の実施(構造計算の義務付けがある場合もあり)。
- 地盤調査を行い、適切な基礎工事を選択する。
- 柱や耐力壁などの耐震補強を施し、強い構造を確保する。
また、地域によっては3階建て住宅を建築するための建築基準法の制限が存在するため、事前に確認しておくことが必要です。特に、防火地域や準防火地域では、耐火性能の高い材料を使用する必要があるため、建築コストが上昇することも考慮する必要があります。

3階建て住宅を建てるための費用相場
建築コストの目安
3階建て住宅の建築コストは構造や仕様によって大きく変動します。一般的に木造・鉄骨造・RC造(鉄筋コンクリート造)の3つの構造があり、それぞれの建築費用の目安は以下の通りです。
最近は資材の値上がりが止まらない為上昇しています。
※図面の形や使用する材料によって価格は大きく変動します。
| 構造の種類 | 坪単価の目安 | 30坪(約99㎡)の場合 | 40坪(約132㎡)の場合 |
|---|---|---|---|
| 木造 | 80万~100万円 | 2400万~3000万円 | 3200万~4000万円 |
| 鉄骨造 | 100万~150万円 | 3000万~4500万円 | 4000万~6000万円 |
| RC造 | 150万~200万円 | 4500万~6000万円 | 6000万~8000万円 |
木造は比較的費用を抑えやすいですが、耐震性や遮音性の面で鉄骨造やRC造に劣ることがあります。一方、RC造は耐震性や断熱性に優れますが、建築コストが高額になる傾向があります。
土地を購入する場合の追加費用
土地を所有していない場合、住宅を建てるために新たに土地を購入する費用が発生します。土地価格は立地や広さ、用途地域によって変動し、一般的に都市部では高額になる傾向があります。
| エリア | 1坪あたりの目安価格 | 30坪の土地価格目安 | 40坪の土地価格目安 |
|---|---|---|---|
| 東京都心部 | 200~500万円 | 6,000万~1億5,000万円 | 8,000万~2億円 |
| 首都圏郊外 | 50~150万円 | 1,500万~4,500万円 | 2,000万~6,000万円 |
| 地方都市 | 30~80万円 | 900万~2,400万円 | 1,200万~3,200万円 |
土地を購入する際には、土地代に加えて仲介手数料や登記費用、測量費用などの費用も考慮する必要があります。
諸費用や税金について
3階建て住宅を建てる際には、建築費用・土地代以外にも各種の諸費用や税金が発生します。主な費用の内訳は以下の通りです。
| 費用の項目 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 設計費用 | 建築費の5~10% | 建築士による設計費用 |
| 建築確認申請費用 | 10万~50万円 | 建築基準法に基づく申請 |
| 登記費用 | 10万~30万円 | 所有権移転や抵当権設定 |
| 不動産取得税 | 固定資産評価額×3% | 住宅用地は軽減措置あり |
| 火災・地震保険 | 10万~50万円 | ローン利用時は加入が一般的 |
| 引越し費用 | 10万~30万円 | 時期や距離で変動 |
特に、住宅ローンを利用する場合は住宅ローンの手数料や保証料が発生するため、事前に銀行の条件を確認しておくことが重要です。また、3階建て住宅は構造が複雑になるため、設計費用が高くなりやすいことにも注意が必要です。

3階建て住宅を安く建てる方法
建築プランをシンプルにする
3階建て住宅を安く建てるためには、設計や間取りをシンプルにすることが重要です。無駄な装飾や複雑な構造を避けることで、施工費を抑えることができます。
間取りをコンパクトにする
部屋数を増やすと壁や扉が多くなり、必然的に建材費や施工費が上がります。できるだけ一つの空間を広く使う設計にすることで、コストダウンが可能です。
総二階・総三階の設計を採用する
上下階の間取りをできるだけ揃える「総二階」「総三階」の設計を採用すると、柱や基礎のコストを削減できます。
設備を標準仕様にする
キッチンや浴室などの住宅設備を標準的なものにすることで、費用を大幅に抑えることができます。
ローコスト住宅の選択肢を検討する
ローコスト住宅を選択することで、予算を抑えながら3階建て住宅を実現できます。これは、無駄を省いた設計や規格化された建材を利用することで建築費を削減できるタイプの住宅です。
ローコスト住宅の特徴
- 間取りやデザインのオプションが限定される
- 厳選した建材を使い、コストを抑える
- 工期が短く、早期入居が可能
特に、都市部の狭小地向けにローコスト住宅を提供するメーカーもあり、狭い土地でも効率良く建築できるプランが用意されています。
中古住宅をリノベーションする
土地付きの中古住宅を購入し、リノベーションすることで、新築よりも安く3階建ての家を手に入れることができます。
中古住宅を活用するメリット
- 土地を新たに購入する必要がない
- 建物の基礎や構造を活かせるためコストが抑えられる
- リノベーションによって最新の設備やデザインに変更可能
ただし、リノベーションには予算をしっかり見積もる必要があります。築年数が古い物件では耐震性や法規制の問題が発生することもあるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが大切です。

土地が無くてもマイホームを建てるための資金計画
住宅ローンの利用方法
土地が無い状態で家を建てる場合、住宅ローンの活用は重要な資金調達方法となります。住宅ローンには様々な種類があり、選択肢によって総返済額や返済計画に大きく影響します。
土地付き住宅ローンと建築条件付き土地ローン
住宅ローンには、土地購入費と建築費をまとめて借りられる「土地付き住宅ローン」や、一定の建築条件がある場合に利用できる「建築条件付き土地ローン」があります。これらのローンを活用することで、効率的に資金を手配できます。
フラット35を活用する
政府系金融機関が提供する「フラット35」は、固定金利型の住宅ローンであり、長期的な資金計画が立てやすい点が魅力です。特に、頭金を抑えて借入可能な商品も存在し、土地を新たに購入する場合でも利用しやすいローンの一つとなります。
つなぎ融資とは?
注文住宅を建てる場合、建築資金を段階的に支払う必要があり、通常の住宅ローンではカバーできない場合があります。そのため、土地購入から建物完成までの間に利用する「つなぎ融資」を活用することで、スムーズな資金調達が可能になります。
自己資金と頭金の目安
3階建て住宅を建てる際、自己資金と頭金がどの程度必要かを把握することも重要です。特に、住宅ローンの審査においては頭金の割合が影響することが多いため、ある程度の準備が求められます。
頭金の相場
一般的に、住宅購入時の頭金は物件価格の20%程度が目安とされています。しかし、フルローンを利用すれば頭金なしでも購入可能な場合があり、その分毎月の返済額が増える点には注意が必要です。
諸費用の準備
住宅ローンの借入金額には、仲介手数料や登記費用、火災保険料などの様々な諸費用が含まれていません。これらは原則的に自己資金でまかなう必要があるため、以下の表に代表的な費用を示します。
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 土地価格の3%+6万円+消費税 | 不動産会社を通じて土地を購入する場合に発生 |
| 登記費用 | 10万円~30万円 | 司法書士へ依頼するケースが一般的 |
| 火災保険料 | 5万円~20万円 | 住宅ローン契約時に加入必須 |
| 固定資産税 | 年間10万円~ | 地域や建物の価格によって異なる |
| 引っ越し費用 | 10万円~30万円 | 荷物量や移動距離による |
補助金や減税制度を活用する
3階建て住宅を建てる際には、国や自治体の制度を活用することで費用負担を軽減できます。以下のような補助金や減税制度をチェックし、効果的に活用しましょう。
住宅ローン減税
住宅ローン減税は、一定期間にわたり住宅ローンの残高に応じた所得税の控除が受けられる制度です。2024年現在、最大控除額や適用条件が変更されることがあるため、最新情報を確認することが重要です。
すまい給付金
収入に応じて最大50万円の給付金が受け取れる「すまい給付金」は、特に土地を購入して3階建て住宅を建てる場合に活用できます。ただし、取得する住宅が一定の要件を満たす必要があります。
ZEH補助金
3階建て住宅を建てる際、省エネ性能の高い「ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」仕様にすることで、国や自治体から補助金を受けられます。特に、断熱性能を向上させることで光熱費の削減にもつながるため、長期的なコスト削減が可能になります。

まとめ
土地が無い場合でも、親族の土地を活用したり借地を利用するなど、さまざまな方法で家を建てることが可能です。また、3階建ての住宅は狭い土地でも十分な居住スペースを確保できるメリットがある一方で、建築費用や耐震性の確保といった課題もあります。
コストを抑えるためには、狭小地向けのハウスメーカーを活用したり、シンプルなプランを選択することが有効です。さらに、住宅ローンや補助金制度を上手に活用することで、資金計画を立てやすくなります。