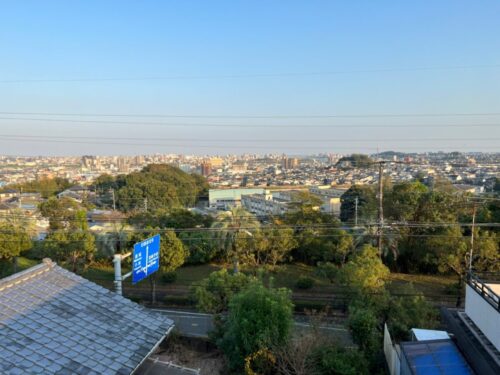強い地盤と弱い地盤の見分け方!地盤調査の重要性と地盤改良のポイント
2025年03月25日

家を建てる際、地盤の強度は非常に重要です。強い地盤なら安全性が高まり、基礎工事のコストも抑えられますが、弱い地盤だと沈下や傾きのリスクが増し、地盤改良が必要になることもあります。本記事では、強い地盤と弱い地盤の見分け方、地盤調査の重要性と方法、さらに必要に応じた地盤改良のポイントを詳しく解説します。失敗しない家づくりのために、地盤の知識を深め、安全な住まいを手に入れましょう。
目次
強い地盤とは 弱い地盤とは
強い地盤の特徴
地盤の強さは、建物の耐久性や安全性に直結する重要な要素です。強い地盤とは、圧縮や沈下に対して高い耐久性を持ち、長期間にわたって安定した状態を保つことができる地盤を指します。
強い地盤の主な特徴には以下のようなものがあります。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 締まりが良い | 粒子が密に詰まっており、水を含みにくく沈下のリスクが低い。 |
| 支持力が高い | 建物の荷重をしっかりと支えることができる。 |
| 水はけが良い | 地下水位が低く、雨水を適切に排水できるため、液状化や沈下のリスクが少ない。 |
| 地層の安定性が高い | 地震時にも揺れが小さく、変形しにくい。 |
一般的に強い地盤とされるのは、岩盤・砂礫層・固結した粘土層などです。これらは施工時の地盤改良が不要であるケースが多く、建物を支えるのに適した条件を備えています。
弱い地盤の特徴
一方で、弱い地盤は、建物の荷重を十分に支えられず、時間の経過とともに沈下や変形が生じる可能性が高い地盤です。
弱い地盤の具体的な特徴を以下の表にまとめます。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 締まりが悪い | 地盤がゆるく、圧力をかけると沈み込みやすい。 |
| 含水比が高い | 地下水位が高く、雨水を吸収しやすいため、ぬかるみやすい。 |
| 支持力が低い | 建物の荷重を支えきれず、不均等沈下が起こりやすい。 |
| 圧縮されやすい | 砂や粘土の粒子が粗く、密度が低いため、時間の経過とともに収縮する。 |
| 液状化リスクが高い | 地下水位の高い砂質地盤では、地震時に液状化現象が発生しやすい。 |
日本国内では、弱い地盤として知られるのが沖積層・埋立地・軟弱粘土層です。これらの地盤では、そのまま建物を建築すると大きな沈下が起こる可能性があるため、地盤改良工事が必要になることが一般的です。
強い地盤と弱い地盤を見分けるポイント
地盤の強さを正確に判断するには、専門的な地盤調査が必要ですが、建築前の段階でも一定の判断基準を持つことは可能です。
以下のようなポイントをチェックすることで、おおよその地盤の状態を把握できます。
| 判別方法 | 強い地盤の目安 | 弱い地盤の目安 |
|---|---|---|
| 過去の土地利用 | 自然のままの丘陵地や台地 | 埋立地、旧河川跡、湿地 |
| 地盤の成り立ち | 砂礫層、岩盤 | 粘土層、沖積層 |
| 雨水の排水状況 | すぐに排水される | 水がたまりやすい |
| 地震時の揺れ方 | 揺れが小さい | 揺れが大きく長く続く |
地盤の強弱は、周辺地域の特性や歴史、建物の沈下履歴などからも推測できます。また、ハザードマップ(自治体が発行する地域の自然災害リスクを示した地図)を活用することで、大まかな地盤の安定性を事前に確認することができます。
ただし、目視や簡易的な方法だけでは正確な判断はできないため、最終的な地盤の強度を確認するには、地盤調査を実施することが不可欠です。

地盤調査の重要性と必要な理由
なぜ地盤調査が必要なのか
住宅や建築物の安全性を確保するため、地盤の強度や特性を事前に調査することが重要です。地盤の状態によっては、地震時の揺れ方が大きくなったり、建物の沈下が発生したりする可能性があります。特に日本は地震や台風など自然災害が多い国であり、軟弱な地盤の上に建築すると長期的な安全を確保できないため、地盤調査は不可欠です。
また、建築基準法でも一定の条件において地盤調査が義務化されており、安全な建築物を設計・施工するためには、地盤の特性を把握したうえで適切な施工方法を選択する必要があります。
地盤調査を行わないリスク
地盤調査を行わずに建築を進めると、以下のような重大なリスクが生じる可能性があります。
| リスク | 影響 |
|---|---|
| 不同沈下 | 建物が均等に沈まず、傾きが発生することでドアや窓が開かなくなるなどの被害が生じる。 |
| 耐震性の低下 | 軟弱地盤では地震の揺れが増幅し、倒壊のリスクが高まる。 |
| 建物の劣化 | 地盤が原因でひび割れや沈下が発生し建物寿命が短くなる。 |
| 修繕費用の増加 | 地盤の影響で問題が発生すると、後から補修や改修を行う必要があり多額の費用が発生する。 |
これらのリスクを防ぐために、新築住宅や建築物を設計する際には、事前に地盤調査を行い、適切な対策を講じることが非常に重要です。
地盤調査のタイミングと手順
地盤調査の適切なタイミング
地盤調査は、建物の設計段階で行うことが理想的です。具体的には、以下のタイミングで実施するのが望ましいです。
- 土地を購入する前に地盤の状態を確認する段階
- 建物の設計が決定する前に、地盤の強度を確認する段階
- 基礎工事を始める前に、地盤に問題がないか最終確認する段階
特に地盤が弱い地域や過去に液状化被害があったエリアでは、建築前に慎重な調査を行うことが推奨されます。
地盤調査の基本的な手順
一般的な地盤調査の流れは以下の通りです。
- 事前情報の収集建築予定地の過去の用途、地質、周辺地域の地盤情報を収集します。自治体が提供するハザードマップや地盤情報を活用することが重要です。
- 試験方法の選定建物の規模や土地の特性に応じて、スウェーデン式サウンディング試験やボーリング調査など適切な調査手法を選択します。
- 地盤調査の実施専門の調査会社が、現場で実際に地盤の強度を測定し、結果を分析します。
- 調査結果の解析取得したデータを基に、地盤の強度や安定性を評価し、必要に応じて地盤改良の提案が行われます。
- 対策の計画と実施地盤の状況に応じて補強工事が必要かどうかを判断し、適切な地盤改良工法が選択されます。
事前に適切な地盤調査を行うことで、長期的に安全な建物を実現することができます。また、地盤の状態によっては追加の補強工事が必要となる場合があるため、調査結果を踏まえた適切な設計を行うことが重要です。

地盤調査の方法とそれぞれの特徴
地盤調査は、土地の地盤の強度や性質を確認するために行われ、建築物の安全性を確保する上で欠かせません。ここでは、代表的な地盤調査の方法とそれぞれの特徴について詳しく解説します。
スウェーデン式サウンディング試験
スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)は、住宅建築などの小規模建築において最も一般的に行われる地盤調査方法です。
3.1.1 スウェーデン式サウンディング試験の特徴
- 調査方法がシンプルで、コストが比較的安い
- 地表から10メートル程度までの地盤の硬さを測定可能
- 小型の機械で手軽に調査できるため、狭い敷地でも実施しやすい
スウェーデン式サウンディング試験の調査方法
先端がネジ状のロッドを地盤に挿入し、荷重を加えながら回転させて貫入抵抗を測定します。この回転数や貫入状態から地盤の軟弱性を判断します。
3.2 ボーリング調査
ボーリング調査は、より詳細な地質情報を取得するために行われる調査方法で、高層ビルや大規模な建築物を建てる際に重視されます。
ボーリング調査の特徴
- 地盤の深部(通常20〜30メートル、場合によっては100メートル以上)まで調査可能
- さまざまな地盤試験を併用することで、正確なデータを取得できる
- コストが高く、時間もかかるため、小規模な建築にはあまり利用されない
ボーリング調査の調査方法
専用のボーリングマシンを使用し、地中に穴を掘りながら土質サンプルの採取や標準貫入試験を行うことで、詳細な地盤データを得ます。
表面波探査法
表面波探査法は、地震波に似た振動を利用して地盤の強度を測定する方法です。
表面波探査法の特徴
- 地盤の密度や剛性を評価できる
- 非破壊検査であり、周囲の環境に影響を与えにくい
- 短時間で広範囲の調査が可能
表面波探査法の調査方法
地表に人工的な振動を発生させ、その波の伝播速度を測定することで、地盤の強度を算出します。波の速さが速いほど地盤が強固であると判断されます。
平板載荷試験
平板載荷試験は、特定の地点で直接的な地盤の支持力を測定できる方法です。
平板載荷試験の特徴
- 地表付近の地盤の直接的な支持力を測定可能
- 試験によって即時に結果が得られる
- 広範囲の調査には向かない
平板載荷試験の調査方法
地面に鋼製の平板を設置し、その上に荷重を段階的に増加させながら沈下量を測定し、地盤の圧縮性や支持力を評価します。
地盤調査方法の比較
各地盤調査方法の特徴を以下の表にまとめました。
| 調査方法 | 調査深度 | 精度 | コスト | 適用範囲 |
|---|---|---|---|---|
| スウェーデン式サウンディング試験 | 〜10m程度 | 簡易 | 低 | 住宅など小規模建築向け |
| ボーリング調査 | 30m以上可能 | 高精度 | 高 | 高層ビル・大規模建築向け |
| 表面波探査法 | 10〜20m程度 | 標準 | 中 | 広範囲の地盤調査 |
| 平板載荷試験 | 地表付近 | 直接計測 | 中 | 地盤の局所的な強度測定 |
これらの地盤調査方法は、それぞれの建築目的やコストに応じて適したものを選択する必要があります。特に、建築基準法に従って適切な地盤評価を行うことで、安全な建築計画を立てることが可能です。

弱い地盤を補強するための地盤改良方法
地盤が弱いと建物の安定性が損なわれ、不同沈下や倒壊のリスクが高まります。そのため、安全な建築を実現するためには地盤改良が不可欠です。ここでは、代表的な地盤改良方法とそれぞれの特徴について詳しく解説します。
表層改良工法
表層改良工法は、地盤表層(通常2m程度)を対象に改良を行う方法です。軟弱地盤の表層部分にセメント系固化材を混ぜて締め固め、地盤の強度を向上させます。
表層改良工法の特徴
- 比較的コストが低く、施工期間も短い
- 2m以内の地盤改良に適している
- 重機を使った施工が可能で、広い範囲の改良が容易
表層改良工法が適しているケース
地盤改良の必要があるが、比較的浅い部分の地盤が軟弱な場合に適用されます。例えば、地表付近のみが軟弱な場合や、建物の荷重が比較的軽いときに有効です。
柱状改良工法
柱状改良工法は、地中にコラム(円柱状)の改良体を作ることで建物の支持力を高める工法です。深さ2m以上の軟弱地盤に対応し、支持層までの地盤を強化します。
柱状改良工法の特徴
- 軟弱地盤が2〜8m程度の深さまである場合に適用できる
- セメント系固化材を使用し、地盤に固い柱を形成する
- 不同沈下の防止に効果的
柱状改良工法が適しているケース
| 適用条件 | 適用可能な地盤 |
|---|---|
| 建物の荷重が比較的重い | 2〜8mの深さに軟弱層が存在する |
| 不同沈下を防ぎたい | 支持層が比較的深い場合 |
鋼管杭工法
鋼管杭工法は、強度の高い鋼管杭を支持層まで打ち込むことで地盤強度を高める工法です。特に、10m以上の深い軟弱地盤に適しています。
鋼管杭工法の特徴
- 支持層が深い場合でも対応可能
- 施工時の振動が少なく、環境への影響を抑えられる
- 確実な支持力が得られ、大規模な建築にも対応可能
鋼管杭工法が適しているケース
支持層が深く、地表からの改良が難しい場合や、高層建築を計画している場合に適用されます。
地盤改良を行う際の注意点
地盤改良を行う際には、以下の点に注意する必要があります。
適切な工法の選定
地盤の性質に合わない改良方法を選択すると、想定した強度が得られない可能性があります。必ず事前に地盤調査を実施し、適切な改良工法を選択することが重要です。
コストと効果のバランス
コストを抑えるためには、過剰な改良を避けることも大切です。ただし、必要以上に工法を簡略化すると地盤沈下のリスクが高まるため、慎重に判断しましょう。
施工実績のある業者の選定
地盤改良には高い技術力が求められるため、経験豊富な業者を選定することが重要です。実績のある業者に依頼し、確実な地盤強化を行うことが求められます。

地盤調査と地盤改良の費用相場
地盤調査の費用
家を建てる前に行う地盤調査は、土地の安全性を確認するために不可欠です。地盤調査にはいくつかの方法があり、それぞれ費用が異なります。以下に代表的な地盤調査の種類と費用の目安を示します。
| 調査方法 | 費用相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| スウェーデン式サウンディング試験 | 5万~10万円 | もっとも一般的な調査方法で、木造住宅などで広く採用されている |
| ボーリング調査 | 20万~50万円 | 詳細なデータが得られるが、費用が高く、大規模建築向け |
| 表面波探査法 | 10万~20万円 | 非破壊で調査可能で、短時間で広範囲のデータ取得が可能 |
| 平板載荷試験 | 10万~30万円 | 地盤の沈下特性を把握できるため、直接基礎を採用する際に適している |
費用は土地の立地や調査会社によって異なるため、複数の業者に見積もりを依頼するとよいでしょう。
地盤改良の費用
地盤調査の結果、地盤が弱いと判定された場合は地盤改良が必要になります。地盤改良の方法によって費用は大きく異なります。
| 地盤改良工法 | 費用相場(1㎡あたり) | 施工対象 |
|---|---|---|
| 表層改良工法 | 5,000~10,000円 | 地盤の浅い部分が軟弱な場合に適用 |
| 柱状改良工法 | 10,000~20,000円 | 深さ2~8m程度の軟弱層がある場合に適用 |
| 鋼管杭工法 | 20,000~40,000円 | 10m以上の深い軟弱地盤で、強固な支持層が必要な場合に適用 |
地盤改良の費用は施工面積・地盤の状況・改良の深さなどによって変わります。そのため、専門業者と事前に十分相談することが重要です。
コストを抑えるためのポイント
地盤調査や地盤改良には高額な費用がかかることがありますが、以下の点に注意すればコストを抑えることが可能です。
- 事前に自治体の地盤情報を確認し、軟弱地盤であるかを把握する
- 複数の調査会社や改良業者から見積もりを取り、比較する
- 適切な地盤調査方法を選び、過剰な調査を避ける
- 必要以上の地盤改良を行わないよう、専門家の意見を参考にする
また、建築会社と契約する際に地盤保証付きのプランを選ぶことで、万が一のトラブルを避けられる場合があります。保証の範囲や条件を確認し、余計な出費を抑えましょう。

地盤の強度を事前に確認する方法
周辺の地盤情報を調べる
家を建てる前に周辺の地盤情報を調べることは非常に重要です。地盤の状態は地域ごとに異なり、過去の開発や自然環境の影響を受けています。以下の方法で、事前に地盤の強度を確認できます。
地質図を確認する
日本各地の地質図は、国土地理院や地方自治体のサイトで公開されています。これらの資料を利用すれば、対象エリアの地盤の構成や強度をおおよそ把握できます。
過去の土地履歴を調べる
以前その場所が沼地、埋立地、田んぼだった場合、地盤が弱い可能性が高いです。地名の由来や古地図を活用して、土地の成り立ちを確認しましょう。
近隣の建物の状況をチェックする
周辺地域の建物に傾きや亀裂があるかどうかも地盤の強度を判断する材料になります。特に、築年数の浅い建物で異常が見られる場合は注意が必要です。
自治体のハザードマップを活用する
多くの自治体ではハザードマップを提供しており、これを活用することで地盤の安全性を確認できます。地盤の強度や災害リスクを知るためには、以下の点をチェックしましょう。
液状化リスクを確認する
特に埋立地や河川沿いでは液状化のリスクが高くなります。自治体のハザードマップには、液状化の危険度が示されていることが多いので確認しましょう。
浸水履歴を調べる
過去に浸水被害が発生した地域は、地盤が軟弱な可能性があります。水害による地盤の軟化も考慮しながら家づくりを進めましょう。
土砂災害の危険区域を確認する
傾斜地や山が近い場所では、地滑りや土砂災害のリスクもあります。ハザードマップに指定されている危険地域に該当するかどうかをチェックしましょう。
専門家に相談する
素人が地盤を見極めるのは難しいため、専門家の力を借りるのも有効です。どのような相談先があるのかを紹介します。
地盤調査会社に依頼する
地盤調査を専門とする会社に調査を依頼すれば、具体的な地盤の状態や改良が必要かどうかを判断できます。特にスウェーデン式サウンディング試験やボーリング調査などの方法で詳細な結果を得ることが可能です。
不動産会社や施工業者に相談する
不動産会社や施工業者は、その地域の地盤傾向を把握していることが多く、簡易的なアドバイスをもらうことができます。地盤の強さに関する実績や情報を提供してもらいましょう。
既存の建築物の基礎を確認する
建築基準に沿った基礎の仕様を採用しているか確認することで、一定の判断材料になります。例えば、深い基礎が必要だった地域は地盤が弱い可能性があります。
事前調査の結果を活かして適切な対策を
これらの方法で得られた情報をもとに、建築前のプランを調整することができます。軟弱地盤であれば地盤改良を検討し、災害リスクの高い場所では盛土や基礎補強を実施することが重要です。
事前の地盤チェックを怠らず、耐久性の高い住宅を建築できるよう準備を進めましょう。

まとめ
地盤の強さは建物の安全性に大きく影響するため、事前の地盤調査が不可欠です。
強い地盤と弱い地盤の特徴を理解し、スウェーデン式サウンディング試験やボーリング調査などの適切な方法で調査を行うことが重要です。
弱い地盤の場合、表層改良工法や柱状改良工法などの地盤改良を適切に実施することで、安全な建築が可能になります。
また、コストを抑えつつ適切な地盤改良を行うためには、自治体のハザードマップを活用し、専門家に相談することが有効です。