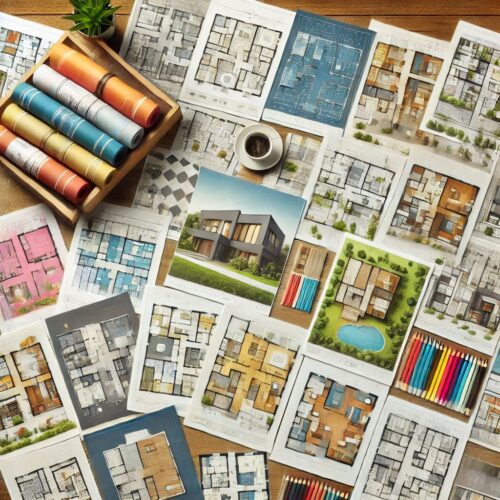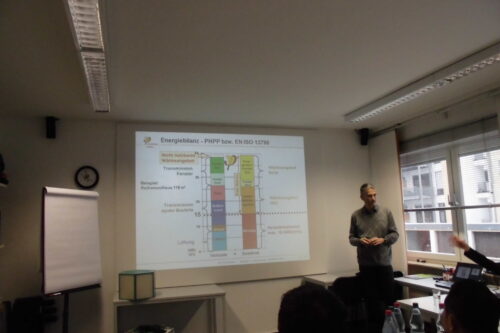【宮﨑県注文住宅】2025年省エネ義務化と宮崎の未来:制度が現実になった今、知るべき変化と対策
2025年10月13日
2025年の省エネ基準適合義務化が目前に迫り、宮崎で注文住宅を検討中の方へ。
この制度が現実となった今、何が変わるのか、そしてどう備えるべきか。
本記事では、宮崎の地域特性を踏まえた具体的な基準の変化から、建築費への影響、高まる住宅性能の重要性、さらに活用できる補助金まで、賢い家づくりのための情報を網羅的に解説します。
未来の住まいを快適かつ経済的に手に入れるための知識がここにあります。

目次
2025年省エネ義務化 宮崎の注文住宅に何が起きるのか
いよいよ現実になった省エネ基準適合義務化の概要
2025年4月1日より、日本におけるすべての新築住宅に対し、省エネ基準への適合が義務化されます。
これは、2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に基づくもので、これまで一部の建物に限定されていた省エネ基準適合義務が、原則としてすべての新築住宅・非住宅に拡大されることになります。
この義務化の背景には、2050年までにカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を実質ゼロにすること)を目指すという政府目標があります。
日本のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野での省エネ対策を加速させることが、この目標達成に不可欠とされています。
具体的には、新築される住宅は「外皮性能基準」と「一次エネルギー消費量基準」の2つの基準を満たすことが求められます。
これらの基準を満たさない場合、建築確認手続きにおいて適合性が認められず、工事に着工することができなくなります。
宮崎の地域区分と省エネ基準の具体的な変化
省エネ基準は、地域ごとの気候特性に合わせて設定されており、日本は1から8までの地域区分に分けられています。
宮崎県は、比較的温暖な気候であることから、多くの地域が「7地域」に区分されています。
2025年からの義務化により、宮崎県を含むすべての地域で、新築住宅は「断熱等性能等級4」かつ「一次エネルギー消費量等級4」以上を満たすことが必須となります。
断熱等性能等級4は、2022年3月までは最高等級とされていましたが、義務化によって実質的な最低等級となります。
宮崎県(7地域)における省エネ基準の具体的な数値は以下の通りです。
| 基準項目 | 宮崎県(7地域)の基準値 | 説明 |
|---|---|---|
| 外皮平均熱貫流率(UA値) | 0.87 W/㎡K以下 | 住宅の内部から外部へ熱がどれだけ逃げやすいか、または外部から内部へ熱がどれだけ侵入しやすいかを示す数値です。この数値が小さいほど断熱性能が高いことを意味します。 |
| 冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値) | 3.0以下 | 冷房期間中に日射によって建物内にどれだけ熱が入り込むかを示す数値です。この数値が小さいほど日射遮蔽性能が高いことを意味します。 |
| 一次エネルギー消費量 | 地域別の基準値以下(BEI値1.0以下) | 住宅で使用されるすべてのエネルギー(冷暖房、換気、給湯、照明など)を一次エネルギー量に換算したものです。再生可能エネルギーによる創エネ量も考慮されます。 |
これらの基準を満たすためには、これまで以上に高い断熱性能を持つ建材の使用や、高効率な設備機器の導入が不可欠となります。
義務化で変わる建築費と住宅の価値
省エネ基準適合義務化は、宮崎の注文住宅の建築費と住宅の価値に大きな変化をもたらします。
建築費への影響
省エネ基準に適合させるためには、高性能な断熱材、高気密サッシ、高効率な給湯器や換気システムなどの導入が必要となるため、建築コストが上昇する可能性があります。
これまで省エネ性能が低い低コスト住宅という選択肢は事実上なくなり、新築住宅の販売価格は全体的に高くなることが予想されます。
しかし、政府は省エネ基準に適合する建築物の建設を奨励するため、補助金制度の拡充など様々な政策支援を打ち出しています。
これらの補助金や税制優遇制度を賢く活用することで、初期費用の負担を軽減することが可能です。
住宅の価値への影響
一方で、省エネ基準適合義務化は、住宅の資産価値向上に寄与すると考えられます。
省エネ性能の高い住宅は、光熱費の削減、快適な室内環境の実現、健康的な暮らしの提供といったメリットがあるため、市場での評価が高まります。
特に、2024年4月から施行された「省エネ性能表示制度」により、住宅の販売・賃貸広告に省エネ性能ラベルの表示が努力義務化されており、消費者は住宅の省エネ性能を一目で判断できるようになりました。
これにより、省エネ性能の低い住宅は市場で敬遠され、資産価値が下がる可能性も指摘されています。
2025年以降は、省エネ基準適合が住宅の「当たり前」となるため、これからの家づくりにおいては、単に基準を満たすだけでなく、さらに上位の性能を目指すことが、長期的な資産価値の維持・向上に繋がるでしょう。

宮崎の注文住宅に求められる新しい性能と快適性
2025年の省エネ基準適合義務化により、宮崎の注文住宅にはこれまで以上に高い省エネ性能が求められるようになります。
これは単に環境負荷を低減するだけでなく、住まう人の快適性と健康、そして住宅の資産価値向上にも直結する重要な変化です。
ここでは、具体的にどのような性能が求められ、それが暮らしにどのような恩恵をもたらすのかを詳しく解説します。
断熱性能と気密性能の重要性が高まる宮崎の住まい
2025年4月以降、新築されるすべての住宅には、建築物省エネ法で定められた省エネ基準への適合が義務付けられます。
この基準は「外皮性能」と「一次エネルギー消費量性能」の2つの要素で評価され、特に外皮性能においては「断熱等性能等級4」以上が必須となります。
宮崎県は日本の地域区分において「7地域」に分類されており、この地域区分に応じて外皮平均熱貫流率(UA値)の基準値が定められています。
宮崎市の場合、断熱等性能等級4を満たすためにはUA値0.87W/㎡K以下を確保する必要があります。
断熱性能とは、住宅の壁、屋根、床、窓といった外皮部分から熱がどれだけ逃げにくいか、あるいは侵入しにくいかを示す性能です。
一方、気密性能は、住宅の隙間をどれだけ少なくし、外気の侵入や室内の空気の漏れを防ぐかを示す性能を指します。
宮崎の気候は比較的温暖であるものの、夏場の高温多湿や冬場の冷え込みも存在するため、高い断熱性能と気密性能を両立させることで、年間を通じて快適な室内環境を維持しやすくなります。
これにより、冷暖房の効率が向上し、光熱費の削減にも大きく貢献します。
高断熱・高気密な住まいは、外気温の影響を受けにくく、一度暖めたり冷やしたりした室温を長時間保つことができます。
これにより、部屋ごとの温度差が小さくなり、家全体が均一な温度に保たれるため、廊下やトイレ、浴室なども快適な空間となります。
また、結露の発生を抑制する効果もあり、カビやダニの繁殖を防ぎ、建物の劣化を抑えることにもつながります。
一次エネルギー消費量基準と設備の進化
省エネ基準適合義務化において、外皮性能と並んで重要視されるのが「一次エネルギー消費量等級4」以上の達成です。
一次エネルギー消費量とは、住宅で消費される暖房、冷房、換気、給湯、照明などの設備機器が年間で消費するエネルギー量を、石油や天然ガスといった自然界から得られる「一次エネルギー」の単位に換算して合計したものです。
これは、いわば住宅の年間光熱費の目安とも言えます。
一次エネルギー消費量を削減するためには、住宅の断熱性能を高めることに加え、エネルギー効率の高い設備機器の導入が不可欠です。
近年では、給湯器や換気設備、照明器具などに省エネ性能の高い製品が多数登場しており、これらを適切に選択することが、一次エネルギー消費量の削減に直結します。
例えば、高効率給湯器(エコキュートやエコジョーズ)、LED照明、熱交換型換気システムなどが挙げられます。
一次エネルギー消費量を構成する主な要素は以下の通りです。
これらの項目において、より省エネ性能の高い設備を選ぶことが、基準達成の鍵となります。
| エネルギー消費項目 | 主な設備例と省エネのポイント |
|---|---|
| 暖房設備 | 高効率エアコン、床暖房(ヒートポンプ式など) |
| 冷房設備 | 高効率エアコン |
| 換気設備 | 熱交換型換気システム(第一種換気など) |
| 給湯設備 | エコキュート、エコジョーズ、ハイブリッド給湯器 |
| 照明設備 | LED照明 |
これらの設備は、日々の暮らしで消費するエネルギー量を大きく左右します。
最新の省エネ設備を導入することで、快適性を損なうことなく、光熱費を抑え、一次エネルギー消費量基準をクリアすることが可能になります。
高断熱・高気密住宅がもたらす健康と快適な暮らし
高断熱・高気密な注文住宅は、省エネ効果だけでなく、住まう人の健康と快適な暮らしに多大なメリットをもたらします。
最も顕著なのは、室内温度の安定による健康リスクの低減です。
冬場にリビングと脱衣所やトイレといった非暖房空間との温度差が大きいと、急激な温度変化により血圧が変動し、ヒートショックを引き起こすリスクが高まります。
高断熱・高気密住宅では、家全体の温度差が小さいため、このヒートショックのリスクを大幅に軽減できます。
また、室内の温度が一定に保たれることで、心血管疾患や呼吸器系疾患のリスクが減少するという研究結果も国内外で報告されています。
世界保健機関(WHO)も、冬場の室温を18℃以上に保つことが健康維持に効果的であると提言しています。
さらに、高気密住宅は計画的な換気システムと組み合わせることで、常に新鮮な空気を供給し、室内の二酸化炭素濃度やハウスダスト、PM2.5などの有害物質を排出することができます。
これにより、アレルギーや喘息の症状改善、インフルエンザなどのウイルス感染リスクの低減にもつながり、家族の健康を守る住環境を実現します。
宮崎の夏場の高温多湿な気候においても、高断熱・高気密住宅は優れた快適性を提供します。
外からの熱気を遮断し、冷房効率を高めることで、少ないエネルギーで涼しく快適な室内を保つことが可能です。
また、適切な湿度管理もしやすくなるため、カビの発生を抑制し、ジメジメとした不快感を軽減します。
冬場は外の冷気をシャットアウトし、暖房で得られた熱を逃がしにくいため、暖かく過ごしやすいだけでなく、結露による窓の濡れやカビの心配も少なくなります。
このように、高断熱・高気密住宅は、宮崎の多様な気候条件に対応し、一年を通じて健康的で快適な暮らしを支える基盤となるのです。

宮崎で義務化に対応する注文住宅を建てるための対策
2025年の省エネ基準適合義務化は、宮崎県で注文住宅を検討する方にとって、家づくりの進め方を大きく変える転換点となります。
この変化を前向きに捉え、より高性能で快適、そして経済的な住まいを実現するための具体的な対策を講じることが重要です。
信頼できる工務店選びと設計のポイント
省エネ義務化に対応した注文住宅を建てる上で、最も重要なのが、確かな知識と技術を持つ工務店を選ぶことです。
また、宮崎の気候風土に適した設計を追求することも欠かせません。
省エネ住宅の実績と専門知識を持つ工務店を選ぶ
工務店選びでは、省エネ住宅の建築実績が豊富であるか、そして省エネ基準やZEH(ゼッチ)に関する専門知識を持っているかを重視しましょう。
特に、ZEHビルダーとして登録されている工務店は、国が定めるZEH基準の住宅を供給する実績とノウハウがあるため、信頼の目安となります。
宮崎県内には、ZEHビルダーとして登録されている工務店やハウスメーカーが多数存在します。
また、高断熱・高気密住宅の施工に長けているかも重要なポイントです。
気密測定の実施や、断熱材の種類・施工方法について丁寧に説明してくれる工務店を選びましょう。
宮崎市にも高気密・高断熱住宅を得意とする工務店があります。
宮崎の気候風土を活かした設計の重要性
宮崎県は地域区分7に該当し、比較的温暖な気候ですが、夏場の強い日差しや台風への対策も考慮した設計が求められます。
- パッシブデザインの活用:日射遮蔽や通風、採光を最適化することで、機械設備に頼りすぎず、自然の力を利用して快適な室内環境を作り出す設計です。宮崎の豊富な日射量を冬は取り込み、夏は遮る工夫が重要になります。
- 断熱材の適切な選定と施工:宮崎の地域区分に合わせた適切な断熱材の種類(グラスウール、ロックウール、高性能フェノールフォームなど)と厚さを選び、断熱欠損のない丁寧な施工が不可欠です。2025年義務化では断熱等性能等級4以上が求められますが、より高い等級を目指すことで、さらなる快適性と省エネ効果が得られます。
- 開口部の性能向上:窓やドアなどの開口部は熱の出入りが大きい部分です。Low-E複層ガラスや樹脂サッシなど、断熱性能の高い建材を選ぶことで、室内の温度変化を抑え、冷暖房効率を高めます。
- 気密性の確保:高断熱性能を最大限に活かすためには、隙間風を防ぐ高気密施工が重要です。気密測定(C値)を実施し、住宅全体の気密性能を数値で確認できる工務店を選ぶと安心です。
- 計画的な換気システムの導入:高気密住宅では、室内の空気質を保つために計画的な換気システムが必須です。熱交換型換気システムなどを導入することで、換気による熱損失を抑えつつ、常に新鮮な空気を保つことができます。
利用できる補助金や税制優遇制度を賢く活用
省エネ性能の高い住宅の取得には、国の補助金や税制優遇制度を活用することで、初期費用の負担を軽減できます。
これらの制度は年度ごとに内容が変更されることがあるため、最新情報の確認が不可欠です。
国の主要な補助金制度
2025年以降も、省エネ性能の高い住宅に対する補助金制度が継続される見込みです。主な制度は以下の通りです。
| 補助金制度名 | 概要 | 主な対象 | 補助金額(目安) |
|---|---|---|---|
| ZEH補助金 | ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及を目的とした補助金。
ZEH、Nearly ZEH、ZEH Orientedなど、性能レベルに応じて補助額が異なります。 |
ZEH基準を満たす新築住宅 | ZEH基準で55万円/戸、ZEH+基準で90万円/戸(2025年度予想) |
| 子育てグリーン住宅支援事業(こどもエコすまい支援事業の後継) | 子育て世帯や若者夫婦世帯による高性能な省エネ住宅
(長期優良住宅、ZEH水準住宅、GX志向型住宅)の新築・購入を支援。 |
子育て世帯、若者夫婦世帯 | 長期優良住宅:80万円/戸、ZEH水準住宅:60万円/戸、GX志向型住宅:160万円/戸(2025年度予想) |
| 地域型住宅グリーン化事業 | 地域の中小工務店が建てる省エネルギー性や耐久性などに優れた木造住宅に対して補助金を交付する制度。 | 国土交通省の採択を受けたグループが建てる木造住宅 | 最大140万円/戸(2025年度版に掲載あり、最新状況は要確認) |
これらの補助金は、それぞれ要件や申請期間が定められています。
工務店と連携し、ご自身の計画に合った補助金を賢く活用しましょう。
税制優遇制度
省エネ性能の高い住宅は、税制面でも優遇措置が受けられます。
- 住宅ローン減税:2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準に適合していなければ住宅ローン減税の対象外となります。省エネ性能に応じて借入限度額が異なり、長期優良住宅やZEH水準の住宅は特に優遇されます。 子育て世帯や若者夫婦世帯には、2025年入居の場合も優遇措置が継続される見込みです。申請には「建設住宅性能評価書」または「住宅省エネルギー性能証明書」が必要となります。
- 不動産取得税・固定資産税の軽減:長期優良住宅の認定など、特定の条件を満たすことで、不動産取得税や固定資産税が軽減される場合があります。
各制度の詳細は、国土交通省や地方自治体のウェブサイト、または税務署で確認することをおすすめします。
ZEH住宅も視野に入れたワンランク上の宮崎の家づくり
2025年の省エネ義務化は、最低限の基準であり、これからの家づくりではZEH(ゼッチ)水準以上の高性能住宅が主流となることが予想されます。
宮崎でワンランク上の快適な暮らしを目指すなら、ZEH住宅を視野に入れることを強くおすすめします。
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは
ZEHとは「Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)」の略称で、住宅の高断熱化と高効率設備による「省エネ」、そして太陽光発電などによる「創エネ」を組み合わせることで、年間の一次エネルギー消費量の収支を実質ゼロ以下にする住宅のことです。
ZEHには、ZEH、Nearly ZEH、ZEH Orientedといった種類があり、それぞれエネルギー削減率や再生可能エネルギー導入の有無などの要件が異なります。
宮崎県では、断熱等級5のUA値「0.60」がZEH基準とされています。
ZEH住宅がもたらす多大なメリット
ZEH住宅は、省エネ義務化基準を上回る性能を持つため、以下のような多岐にわたるメリットを享受できます。
- 光熱費の大幅削減:高い断熱・省エネ性能と太陽光発電による創エネで、電気代やガス代などの光熱費を大幅に抑えることが可能です。余った電気を売電することで、家計にゆとりが生まれることもあります。
- 快適な室内環境:高断熱・高気密により、冬は暖かく夏は涼しい、温度差の少ない快適な住空間が実現します。ヒートショックのリスク軽減にもつながります。
- 資産価値の向上:省エネ性能が高い住宅は、将来的に市場での評価が高まり、資産価値が向上する傾向にあります。
- 災害時のレジリエンス:太陽光発電システムと蓄電池を組み合わせることで、停電時にも一定の電力を確保でき、災害に強い住まいとなります。
- 環境負荷の低減:CO2排出量の削減に貢献し、地球温暖化対策や持続可能な社会の実現に寄与します。
宮崎でZEHを実現するためのポイント
宮崎でZEH住宅を建てるには、地域の特性を最大限に活かすことが重要です。
- 豊富な日射量を活かした太陽光発電の導入:宮崎県は日照時間が長く、太陽光発電に適した地域です。効率的な太陽光発電システムの導入は、ZEH達成の大きな鍵となります。
- 宮崎の温暖な気候に合わせた断熱・気密計画:過剰な断熱ではなく、宮崎の気候に合わせた最適な断熱・気密設計を行うことで、コストと性能のバランスを取りながら快適性を追求できます。
- 信頼できるZEHビルダーとの連携:ZEHの設計・施工には専門的な知識と技術が必要です。ZEHビルダーとして登録され、実績豊富な工務店と協力することで、スムーズかつ確実にZEH住宅を実現できます。

2025年以降の宮崎の住宅市場と未来の暮らし
義務化がもたらす宮崎の注文住宅の資産価値向上
2025年の省エネ基準適合義務化は、宮崎の注文住宅市場に長期的な影響を与え、特に住宅の資産価値向上に大きく寄与すると考えられます。
義務化された基準を満たす住宅は、そうでない住宅と比較して、将来的に高い評価を受ける可能性が高まります。
これは、エネルギー消費量が少なく、光熱費の負担が軽減されるため、住み続ける上での経済的メリットが大きいからです。
良い省エネ住宅を選ばないと、将来的に資産価値に大きな影響が出る可能性が指摘されています。
中古住宅市場においても、高断熱・高気密といった省エネ性能が高い住宅は、購入希望者にとって魅力的な選択肢となり、結果として売却時の資産価値を維持、あるいは向上させる要因となります。
国土交通省も、住宅の省エネルギー性能の向上を推進しており、住宅性能表示制度の普及を通じて、消費者が省エネ性能を分かりやすく把握できるように努めています。
また、省エネ性能の高い住宅は、住宅ローン減税や固定資産税の減額措置といった税制優遇の対象となる場合があり、これも資産価値を裏付ける重要な要素です。
環境負荷低減と持続可能な社会への貢献
省エネ基準適合義務化は、個々の住宅の性能向上に留まらず、宮崎県全体、ひいては日本全体の環境負荷低減と持続可能な社会の実現に大きく貢献します。
住宅のエネルギー消費を削減することは、温室効果ガスの排出量削減に直結し、地球温暖化対策の重要な一翼を担います。
国土交通省・経済産業省・環境省は、2050年カーボンニュートラル実現に向けた住宅・建築物の対策を公表しており、住宅部門における省エネ対策の強化がその中心に据えられています。
家庭部門からのCO2排出量削減は、国が掲げる2050年カーボンニュートラルの目標達成に向けた不可欠な要素であり、省エネ性能の高い住宅は、冷暖房に頼りすぎない快適な室内環境を提供し、エネルギーの無駄遣いを抑制します。
住民一人ひとりが省エネ住宅に住むことで、地域全体のエネルギー消費量が減少し、エネルギー自給率の向上や災害時のレジリエンス強化にも繋がる可能性があります。

まとめ
2025年省エネ義務化は、宮崎の注文住宅において避けられない変化ではなく、むしろ未来への投資です。
この制度が現実となった今、高断熱・高気密といった省エネ性能は、快適な暮らしと健康を守り、住宅の資産価値を高める上で不可欠となります。
信頼できる工務店を選び、利用可能な補助金や税制優遇制度を賢く活用することで、初期費用を抑えつつ、長期的に見て経済的で環境にも優しい住まいを実現できます。
宮崎の豊かな自然と調和し、持続可能な未来へ貢献する住まいづくりを、今こそ始めましょう。