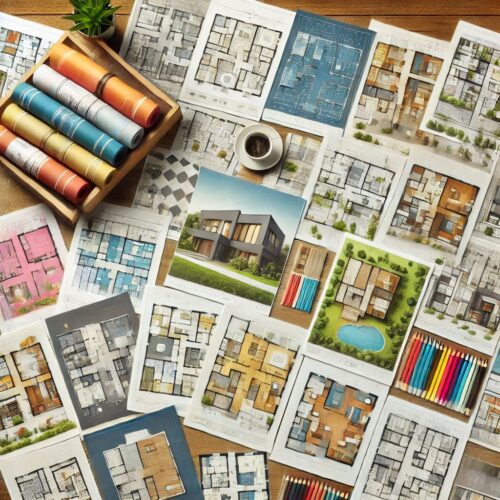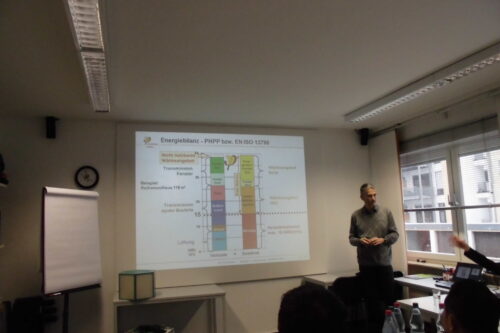宮﨑県で注文住宅を建てるなら知っておきたい!せんぐまき・餅まきの深い由来と意味
2025年07月21日

宮崎で注文住宅を建てる際に知っておきたい「せんぐまき・餅まき」の深い由来と意義を解説。
古代から九州で広まり宮崎県で独自に発展した歴史を紹介し、工事安全祈願や豊穣祈願、地域コミュニティの絆づくりとしての役割を明示。
さらに日取り選定や餅・縁起物の準備、当日の進行から成功事例や参加者の声まで網羅し、棟上げを成功に導くポイントを提示し、安心して棟上げに臨むための知識をお届けします。
目次
せんぐまきと餅まきの基本を理解
せんぐまきと餅まきの定義と違い
「せんぐまき」と「餅まき」は、どちらも建築の上棟式や新築祝いの際に行われる撒きもの行事ですが、撒く品目や行われる場面、呼称に違いがあります。以下の表で両者の主な相違点をまとめました。
| 項目 | せんぐまき | 餅まき |
|---|---|---|
| 名称の由来 | 「千種(せんぐさ)」とも書き、古くは豆や穀物など多種多様な撒きものを意味 | 「餅」を主に撒くことからそのまま呼称 |
| 撒く品目 | 米、豆、落花生、菓子袋など多彩 | 紅白餅、鏡餅をくずしたものが中心 |
| 主催・用途 | 上棟式や地鎮祭など工事安全祈願が主目的 | 新築祝いや地域祭礼、神社の例大祭など幅広い場面で実施 |
| 地域的特徴 | 西日本を中心に「せんぐまき」の呼称と形式が定着 | 全国的に行われ、特に四国・九州で盛ん |
| 参加者の楽しみ | 多彩な品目を狙うワクワク感 | 餅をキャッチするスリルと縁起の良さ |
宮﨑県の伝統行事としての概要
宮﨑県では、古くから上棟式や神社例祭の際にせんぐまき・餅まきを行い、工事の安全や豊作祈願、地域住民との交流を深めてきました。
特に県北や県南の集落では、地元工務店や施主が上棟式のクライマックスとして盛大に餅を撒き、近隣住民や施工関係者を招いて賑やかに祝います。
開催時期は一般的に春から秋にかけての晴れの日が選ばれ、施主や工務店が紅白餅のほか干物、飴玉、小銭などを用意します。
地域の子どもから高齢者まで幅広い世代が参加し、一つの袋をめぐって笑顔や歓声が飛び交うのが特色です。
また、最近ではSNS映えや地域プロモーションを兼ねて、地元産品を景品として混ぜるケースも増加中です。
伝統を受け継ぎつつ、新たな交流の場としてのせんぐまき・餅まきが宮﨑県の注文住宅文化に根づいています。

せんぐまきと餅まきの由来と歴史
古代から中世にかけての起源
日本における餅まきやせんぐまきの起源は、稲作定着期の奈良~平安時代に遡ります。
当時、新嘗祭(にいなめさい)などの神事で収穫物の粟や稲穂、餅を神前に供え、神恩にあずかった残りを村人に分け与えたことが始まりとされます。
神への感謝とともに「余剰の福」を分かち合う祭祀形態が、のちに餅まきや銭まき(せんぐまき)の原型となりました。
| 時代 | 背景と特徴 |
|---|---|
| 奈良~平安時代 | 新嘗祭での余剰餅・穀物の分配。神農信仰と結びつく。 |
| 鎌倉~室町時代 | 社寺造営や強豪武士の屋敷建築で、施工安全祈願として「餅や銭」を配る記録。 |
江戸時代以降の広がり
九州地方での展開
江戸時代になると、伊勢神宮参詣の流行に伴い講中が組織化。
講中の繁栄を願い、参拝先で餅や銭を撒く習慣が地方に波及しました。
とくに九州では、海上交易や農業集落で棟上げ式(じょうとうしき)の際に餅まき・せんぐまきを行う風習が定着し、やがて年中行事として定期的に開催されるようになります。
宮﨑県ならではの発展
宮﨑県では鎌倉時代後期に青島神社の社殿再興記録が残り、その際に「棟札撒き」(のちのせんぐまき)を行った文献があります。
江戸中期以降、砂糖製菓業と畜産が発達した日向地方では、餅に加えて砂糖菓子や小銭を一緒に撒く豪華版が広まりました。
これにより地域ごとの特色が生まれ、現在のように「せんぐまき」と「餅まき」を併せて行う形が完成しました。

注文住宅におけるせんぐまきと餅まきの役割
宮﨑県で新築の注文住宅を建てる際、せんぐまきや餅まきは単なるお祝いイベントではなく、「工事の安全」と「地域とのつながり」を祈る大切な儀式です。
施工の節目ごとに行うことで、地鎮祭や上棟式と合わせ、住まいの堅牢性と入居後の繁栄を願う意味を持ちます。
工事安全祈願と豊穣祈願
せんぐまき・餅まきは、古来より木造建築の要所で行われてきた上棟儀礼の一部です。
上棟式の場で棟梁や施主が棟木にお札を打ち込み、工事関係者の安全と家屋の堅牢を祈ったのち、餅や縁起物をまいて厄をはらいます。
さらに、五穀豊穣や家族繁栄を願う意味が重ねられ、入居後の豊かな暮らしを後押しします。
| 儀式 | 祈願内容 | 実施タイミング |
|---|---|---|
| せんぐまき | 建物の骨組み強化と工事関係者の安全祈願 | 上棟式(棟木取付け時) |
| 餅まき | 五穀豊穣と入居後の家族繁栄祈願 | 上棟後または竣工間近 |
地域コミュニティの絆づくり
せんぐまき・餅まきは、近隣住民や工務店スタッフ、建築関係者が一堂に会する貴重な機会でもあります。
参加者同士が軽く声を掛け合い、餅やお菓子を受け取ることで自然な交流が生まれ、町内会や自治体との関係強化につながります。
特に宮﨑県では、世代を超えた交流を大切にする風土が根付いており、新築現場の活気を通じて「お互いに工事を見守る意識」「子どもから高齢者まで顔の見える関係」を築く効果が高く評価されています。

宮﨑県の注文住宅でせんぐまきを行う準備と流れ
日取りと会場設営
せんぐまきを行う日は、地域で慣習的に重視される六曜や天候予報を参考に決定します。
一般的には「大安」「友引」を選び、晴天が見込まれる時期を狙いましょう。
当日は近隣への挨拶と案内を事前に済ませ、道路や駐車スペースの確保を行います。
会場設営では、以下のポイントを押さえて安全かつスムーズな進行を実現します。
- 足場や資材が残る建築現場では、飛散防止ネットや養生マットを設置
- 来場者用の通路と待機スペースを区画紐やパイプ椅子で明示
- 司会用のマイク・スピーカー、一時保管用のテーブルやかごを準備
- 子どもや高齢者が参加しやすいよう、段差解消のスロープや手すりを用意
餅や縁起物の選び方
せんぐまきで用いる品目は、「紅白餅」を中心に、地域らしい縁起物を組み合わせるのが一般的です。
数量は参加者数の2割増しを目安に用意し、余裕を持たせましょう。以下の表は代表的な品目と準備時期の目安です。
| 品目 | 数量目安 | 準備時期 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 紅白餅(丸餅) | 参加者×2個+予備20% | 前日 | 風呂敷で包むと拾いやすい |
| お菓子(せんべい・駄菓子) | 参加者×1袋 | 前日 | 子ども向けの小分け包装 |
| 小銭(500円玉) | 20枚程度 | 当日朝 | 五円玉を混ぜると更に縁起が良い |
| 縁起物(昆布・栗・鰹節) | 各10~20個 | 前日 | 乾物は湿気対策を |
前日に買い出しを済ませ、汚れないよう新聞紙やトレーで保管します。
当日は冷え込みに備え、蓋付きの容器や保温バッグで持ち運びましょう。
当日の進行スケジュール
進行は時間厳守で行うことで、参加者の安心感を高めます。以下の表は典型的なスケジュール例です。
| 時間 | 内容 | 担当 |
|---|---|---|
| 09:00~10:00 | 会場最終チェック・備品配置 | 施工会社スタッフ |
| 10:00~10:30 | 関係者集合・開会の挨拶 | 施主 |
| 10:30~11:00 | 工事安全祈願(略式の地鎮祭) | 神職または地元の屋台講 |
| 11:00~11:30 | せんぐまき開始 | 施主・施工会社代表 |
| 11:30~12:00 | 後片付け・ご近所へのお礼回り | 施主・家族 |
終了後は集まった道具や残りの品目を速やかに回収し、近隣への騒音やごみ散乱を防止します。最後に参加者へお礼の声掛けと、完成予定日を記した案内チラシを配布すると好印象です。

実例で見る宮﨑県のせんぐまきと餅まき
成功事例のポイント
| 事例 | 開催地 | 実施時期 | 特徴的な工夫 |
|---|---|---|---|
| 事例1 | 宮崎市(清武町) | 2022年6月(上棟式に合わせて) | 地元産の飫肥杉小餅を使用し、大工棟梁が挨拶で伝統行事の由来を解説 |
| 事例2 | 都城市(山田町) | 2023年11月(完成見学会と同日開催) | 家族全員参加型プログラムを導入し、子供用の「福くじ餅」を用意 |
| 事例3 | 延岡市(北方町) | 2021年12月(地鎮祭後の安全祈願として) | 集落全体を招き、地鎮祭・せんぐまき・餅まきを一連で実施し地域活性化に貢献 |
上記のように、宮﨑県内では上棟式や地鎮祭と組み合わせることでせんぐまき・餅まきの儀式をより伝統行事らしく演出しています。
大工棟梁や施工会社の進行管理の下、餅や縁起物には地元産材料を使い「地域の絆」を深める工夫が見られます。
参加者の声と反響
「上棟式で初めてせんぐまきを体験しましたが、昔ながらの儀式が大工さんの解説とともに楽しめて良かったです。飫肥杉の小餅は香り豊かで、縁起物として持ち帰る価値がありました。」(宮崎市・30代女性)
「都城での完成見学会での餅まきに子供と参加しました。『福くじ餅』では当たり付きのミニ餅を引くワクワク感があり、家族全員で盛り上がりました。地域コミュニティの温かさを感じます。」(都城市・40代男性)
「延岡市北方町のせんぐまきでは、地鎮祭から参加できたのが印象的でした。全戸を招いての一大イベントになり、集落の人同士の交流が生まれました。工事安全祈願としての意味も深く、安心して住めそうです。」(延岡市・50代女性)
これらの声から、せんぐまき・餅まきはただの餅撒きではなく、工事安全祈願や豊穣祈願をはじめ、地域活性化やコミュニティづくりに大きく寄与していることがわかります。

まとめ
宮崎県の注文住宅におけるせんぐまき・餅まきは、古代からの安全祈願と豊穣祈願を現代に継承。施工中の無事と完成後の繁栄を願いながら、地域住民を巻き込むことでコミュニティを活性化。準備や進行のポイントを押さえ、伝統を今に息づかせることが成功の鍵。日取りや縁起物選び、当日の流れを事前に確認し、参列者への配慮を忘れずに。宮崎市や延岡市など各地で親しまれる風習を活かし、注文住宅に彩りと結束力をもたらそう。