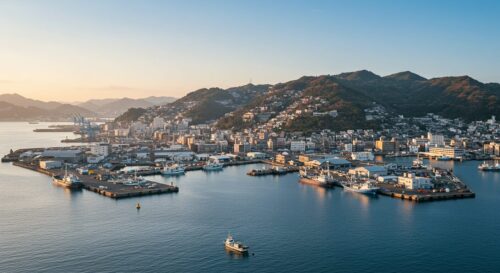南海トラフ地震:地震調査委員会による発表速報と最新の見解
2025年09月27日
南海トラフ地震に関する地震調査委員会の発表について、その速報と最新の見解を深掘りします。
この記事では、地震調査委員会の権威ある役割から、南海トラフ地震の長期評価や臨時情報の種類と基準、現在の発生可能性、そして専門家が推奨する備えまでを網羅的に解説。不確かな情報に惑わされず、正確な知識と冷静な判断力を養い、適切な防災行動へと繋がる情報になります。

目次
地震調査委員会とは 南海トラフ地震の権威ある情報源
地震調査委員会の役割と組織概要
地震調査委員会は、日本における地震活動の総合的な調査観測、評価を推進するために設置された政府機関です。
正式名称は「地震調査研究推進本部 地震調査委員会」といい、1995年の阪神・淡路大震災を契機に制定された地震防災対策特別措置法に基づき設立されました。
その主な役割は、日本全国の地震活動に関する科学的知見を集約し、長期的な地震発生の可能性評価(長期評価)や、活発な地震活動に対する臨時的な評価を公表することにあります。
これにより、国民や行政機関が地震に対する適切な備えを行うための、科学的根拠に基づいた情報を提供しています。
委員会は、大学や研究機関の専門家、気象庁などの関係機関のメンバーで構成されており、最新の観測データや研究成果を基に、透明性のある形で評価を行っています。
その活動は、地震の発生メカニズムの解明、地震発生予測技術の向上、そしてそれらの情報を社会に還元することを通じて、日本の地震防災対策の中核を担っています。
南海トラフ地震の調査における重要性
南海トラフは、日本列島が位置する大陸プレートの下に、海洋プレートであるフィリピン海プレートが年間数cmの割合で沈み込んでいる場所です。
この沈み込みに伴い、二つのプレートの境界には大規模なひずみが蓄積されており、過去1400年間を見ると、約90年~270年の間隔でこのひずみを解放するマグニチュード8~9クラスの巨大地震が繰り返し発生してきました。
近年では、昭和東南海地震(1944年)や昭和南海地震(1946年)がこれに該当し、これらの地震から約80年が経過していることから、南海トラフにおける次の大地震発生の可能性が極めて高まっているとされています。
地震調査委員会は、南海トラフ地震に関する最も権威ある情報源として、この地域の地震活動の長期評価を定期的に更新し、その発生可能性や規模、影響範囲について詳細な見解を発表しています。
地震調査研究推進本部では、南海トラフをこれまでのような南海・東南海領域という区分をせず、南海トラフ全体を一つの領域として捉え、この領域では大局的に100年~200年で繰り返し地震が起きていると仮定して、地震発生の可能性を評価しています。
この評価は「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)」として公表されています。
この評価では、地震の規模をM8~M9クラスと想定し、今後30年以内の発生確率を非常に高いランク(Ⅲランク:26%以上)と位置づけています。
具体的な確率値としては、すべり量依存BPTモデルでは60%~90%程度以上、BPTモデルでは20%~50%と提示されており、防災対策の推進においては、積極的な行動を促す観点から、高い方の確率値(60%~90%程度以上)を採用することが望ましいとされています。
これらの情報は、政府や地方自治体が策定する防災計画の基礎となり、国民一人ひとりの防災意識向上にも不可欠な役割を果たしています。
また、南海トラフでは、過去の地震において震源域の広がり方や発生様式に多様性が見られることが指摘されており、地震調査委員会はこうした複雑な要素も踏まえ、最新の科学的知見に基づいた評価を継続的に行っています。
例えば、東海・東南海・南海地震の連動性評価研究プロジェクトなど、多岐にわたる研究プロジェクトを通じて、より精度の高い予測と防災対策への貢献を目指しています。
地震調査委員会は、毎月の地震活動の評価や臨時情報についても発表しており、これらの情報は南海トラフ地震への備えにおいて重要な指針となります。
南海トラフ地震の将来の発生可能性に関する詳細な評価は以下の通りです。
| 評価項目 | 内容 |
|---|---|
| 地震の規模 | M8~M9クラス |
| 海溝型地震としての発生確率ランク(30年以内) | Ⅲランク(高い):26%以上 |
| 地震発生確率値(30年以内) |
※防災対策では、高い方の確率値(60%~90%程度以上)を採用することが望ましいとされています。 |
| 地震後経過率 |
|
| 平均発生間隔(ベイズ事後平均値) |
|
南海トラフ地震の基礎知識 再確認すべきポイント
南海トラフ地震の発生メカニズムと過去の履歴
南海トラフは、日本列島が位置する大陸プレートの下に、海洋プレートであるフィリピン海プレートが年間数センチメートルの速度で南側から沈み込んでいる場所です。
このプレートの沈み込みに伴い、二つのプレートの境界には巨大なひずみが蓄積されています。
過去約1400年間の記録によると、南海トラフでは約90年から270年の間隔で、この蓄積されたひずみを解放する大規模な海溝型地震が発生してきました。
近年では、1944年の昭和東南海地震と1946年の昭和南海地震がこれに該当します。
これらの地震から80年近くが経過しており、南海トラフにおける次の大地震発生の可能性が高まっていると考えられています。
南海トラフで過去に発生した大地震は、その震源域の広がり方や発生様式に多様性が見られます。
そのため、次に発生する地震の正確な震源域を現在の科学的知見で予測することは困難です。
地震調査委員会では、南海トラフ全体を一つの領域として捉え、大局的に100年から200年の周期で地震が繰り返されていると仮定して、地震発生の可能性を評価しています。
過去の南海トラフ地震の発生状況は以下の通りです。
| 地震名 | 発生年 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 慶長地震 | 1605年 | 揺れは小さかったものの、大きな津波が記録された特異な地震。明治三陸地震のような津波地震であった可能性が高いとされています。 |
| 宝永地震 | 1707年 | 津波堆積物などの調査から、昭和南海地震(1946年)や安政南海地震(1854年)の震源域より西に広がっていた可能性が指摘されています。 |
| 安政東海地震 | 1854年 | 駿河湾の奥まで断層のすべりが広がったと考えられています。 |
| 昭和東南海地震 | 1944年 | 御前崎より西側で断層のすべりが停止しました。 |
| 昭和南海地震 | 1946年 | 昭和東南海地震と数年の時間差をもって発生しました。 |
また、南海トラフでは、プレート境界だけでなく分岐断層が活動することによる地震も過去に発生していたと指摘されています。
想定される規模と影響範囲
南海トラフで次に発生が想定される地震は、マグニチュード(M)8から9クラスの巨大地震です。地震調査委員会は、南海トラフにおける海溝型地震の今後30年以内の発生確率を非常に高いと評価しており、そのランクは「Ⅲランク(高い)」に分類されています。
海溝型地震の発生確率ランクは、今後30年以内の地震発生確率に基づき、以下の基準でランク分けされています。
| ランク | 発生確率(30年以内) | 評価 |
|---|---|---|
| Ⅲランク | 26%以上 | 高い |
| Ⅱランク | 3%~26%未満 | やや高い |
| Ⅰランク | 3%未満 | 低い |
| Xランク | 不明 | すぐに地震が起きることを否定できない |
具体的な地震発生確率値(30年以内)については、すべり量依存BPTモデルでは60%~90%程度以上、BPTモデルでは20%~50%と評価されています。
防災対策を推進する上で具体的な確率値が必要な場合、防災では積極的な行動を促すことが基本であるため、高い方の確率値(60%~90%程度以上)を採用することが望ましいとされています。
現在の地震後経過率は、すべり量依存BPTモデルで0.82、BPTモデルで0.67です。平均発生間隔(ベイズ事後平均値)は、すべり量依存BPTモデルで95.9年、BPTモデルで117.4年と評価されています。
これらの評価は、南海トラフ全体を一つの領域として、大局的に100年から200年で地震が繰り返されているという仮定に基づいています。
より詳細な情報は、南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)で確認できます。
このM8~M9クラスの巨大地震が発生した場合、その影響は広範囲に及びます。
特に、太平洋沿岸地域では甚大な津波被害が想定されており、長周期地震動による高層ビルへの影響も懸念されています。
地震動予測地図や津波評価に関する詳細な情報は、地震調査研究推進本部のウェブサイトなどで確認することができます。

地震調査委員会による南海トラフ地震の発表内容
地震調査委員会は、南海トラフ地震に関する最新の科学的知見に基づき、長期的な評価と、異常な現象が観測された際の臨時情報について発表しています。
これらの発表は、地震防災対策を検討する上で極めて重要な情報源となります。
長期評価の概要と更新情報
地震調査委員会は、南海トラフにおける大規模地震の発生可能性について「長期評価」として公表しており、定期的にその内容を更新しています。
この評価では、南海トラフ全体を一つの領域として捉え、大局的に100~200年の間隔で繰り返し地震が発生していると仮定して、将来の地震発生可能性を評価しています。
南海トラフで発生する地震は、マグニチュード(M)8~M9クラスの海溝型地震と想定されており、今後30年以内の発生確率は「Ⅲランク(高い)」に分類されています。
具体的には、すべり量依存BPTモデルでは60%~90%程度以上、BPTモデルでは20%~50%と評価されています。
防災対策においては、積極的な行動を促す観点から、高い方の確率値(60~90%程度以上)を採用することが望ましいとされています。
過去1400年間を見ると、南海トラフでは約90~270年の間隔で大地震が発生しており、近年では昭和東南海地震(1944年)や昭和南海地震(1946年)がこれに該当します。
これらの地震から約80年が経過し、次の大地震発生の可能性が高まっている状況です。
地震調査委員会による長期評価の詳細は、「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)」で確認できます。
| 評価項目 | すべり量依存BPTモデル | BPTモデル |
|---|---|---|
| 地震発生確率値(30年以内) | 60%~90%程度以上 | 20%~50% |
| 地震後経過率 | 0.82 | 0.67 |
| 平均発生間隔(ベイズ事後平均値) | 95.9年 | 117.4年 |
臨時情報の種類と発表基準
南海トラフ地震においては、将来的にM8クラスの大地震が発生し、残りの領域においても連動して大地震が発生する可能性が高まる「半割れ」ケースなどの「異常な現象」が観測される可能性があります。
このような異常な現象が観測された場合には、地震調査委員会が「南海トラフ地震臨時情報」を発表することがあります。
南海トラフ地震臨時情報とは
南海トラフ地震臨時情報は、南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、それが大規模な地震発生につながる可能性が高まったと判断された場合に発表される情報です。
これは、まだ大地震が発生していない段階で、住民や企業が防災対応を検討し、準備を始めるための時間的猶予を与えることを目的としています。
例えば、一部の領域でM8クラスの地震が発生し、残りの領域でも連動して地震が発生する可能性が高まる「半割れ」のようなケースが想定されます。
臨時情報発表時の政府・自治体の対応
南海トラフ地震臨時情報が発表された場合、政府や地方自治体は、住民・企業等に対して具体的な防災対策の実行を促すための対応を行います。
文部科学省では、「異常な現象」が起こった後の地震活動の推移を科学的・定量的に評価するための研究開発や、「異常な現象」が観測された場合の住民・企業等の防災対策のあり方、防災対応を実行するにあたっての仕組みについて調査研究を進めています。
これにより、臨時情報が発表された際には、地域の実情に応じた避難計画の見直しや物資の備蓄、避難経路の確認など、迅速かつ効果的な防災行動がとれるよう、連携した対応が求められます。

最新の見解と今後の展望
南海トラフ地震は、日本列島が位置する大陸プレートの下に、フィリピン海プレートが年間数センチメートルの割合で沈み込むことで、プレート境界にひずみが蓄積され発生する大規模な地震です。
過去1400年間を振り返ると、約90年から270年の間隔で大地震が発生しており、近年では昭和東南海地震(1944年)や昭和南海地震(1946年)がこれに該当します。
これらの地震から約80年が経過し、次の大地震発生の可能性が高まっているとされています。
現在の南海トラフ地震発生可能性
地震調査委員会による最新の長期評価では、南海トラフで発生する地震の規模はM8~M9クラスと想定されています。
今後30年以内の発生確率は「Ⅲランク(高い)」に分類されており、具体的な確率値としては、すべり量依存BPTモデルでは60~90%程度以上、BPTモデルでは20~50%と評価されています。
防災対策を推進する上では、より積極的な行動を促すため、高い方の確率値(60~90%程度以上)を採用することが望ましいとされています。
南海トラフ地震の発生可能性に関する詳細な評価は、地震調査研究推進本部による「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)」で確認することができます。
以下に、将来の地震発生の可能性に関する詳細な評価をまとめます。
| 評価項目 | すべり量依存BPTモデル | BPTモデル |
|---|---|---|
| 地震の規模 | M8~M9クラス | |
| 海溝型地震としての発生確率ランク(30年以内) | Ⅲランク(高い) | |
| 地震発生確率値(30年以内) | 60%~90%程度以上 | 20%~50% |
| 地震後経過率 | 0.82 | 0.67 |
| 平均発生間隔(ベイズ事後平均値) | 95.9年 | 117.4年 |
地震調査委員会は、南海トラフ全体を一つの領域と捉え、この領域では大局的に100~200年で繰り返し地震が発生していると仮定して、地震発生の可能性を評価しています。
専門家が語る南海トラフ地震への備え
過去に南海トラフで発生した大地震は、その震源域の広がり方に多様性があり、また、南海地域と東海地域での地震が同時に、あるいは数年以内の時間差で発生するケースも確認されています。
例えば、昭和東南海地震(1944年)と安政東海地震(1854年)では震源域が異なり、宝永地震(1707年)や慶長地震(1605年)のような特異な地震の存在も指摘されています。
分岐断層による地震の発生も過去にはあったとされており、次に発生する地震の震源域を正確に予測することは、現在の科学的知見では困難です。
このような多様な発生パターンを考慮し、専門家は南海トラフ地震への多角的な備えの重要性を訴えています。
文部科学省では、「異常な現象」が観測された際の地震活動の推移を科学的・定量的に評価するための研究開発や、住民・企業等の防災対策のあり方、防災対応の仕組みについて調査研究を進める「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト」などを実施しています。
具体的な備えとしては、まず自身の居住地域の地震リスクを把握することが不可欠です。
地震調査研究推進本部が公開している「全国地震動予測地図」や、防災科学技術研究所の「地震ハザードステーション(J-SHIS)」などを活用し、将来の地震による揺れの強さや津波の可能性を確認することが推奨されます。
特に、高層ビルなどで問題となる長周期地震動についても、予測地図が作成されており、適切な対策を講じる必要があります。
また、政府や地方自治体も南海トラフ巨大地震対策として、地域防災計画の策定やハザードマップの公開、避難訓練の実施など、様々な取り組みを行っています。
内閣府の南海トラフ巨大地震対策のページや、各都道府県・市町村の防災情報ポータルサイトなどを参照し、地域の具体的な防災計画や避難場所、避難経路などを事前に確認しておくことが、命を守る上で極めて重要です。

まとめ
南海トラフ地震は、いつ発生してもおかしくない状況が続いており、地震調査委員会による発表は、私たちにとって最も信頼できる情報源です。
長期評価や臨時情報の意味を正しく理解し、常に最新の情報に耳を傾けることが極めて重要です。
この地震は広範囲に甚大な影響を及ぼすことが想定されるため、政府や自治体の取り組みに加え、私たち一人ひとりが日頃から具体的な防災対策を講じ、地域社会全体で備えを強化していくことが、被害を最小限に抑えるための喫緊の課題であり、最も重要な結論と言えるでしょう。