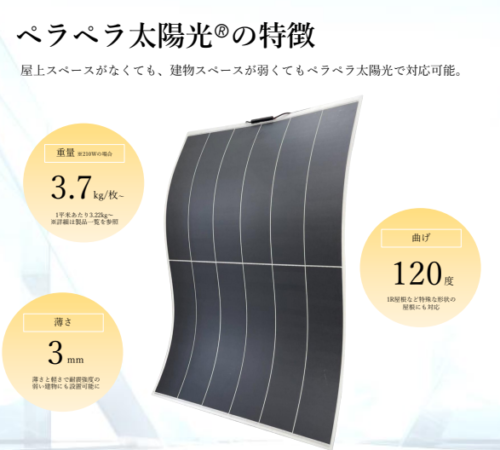なぜ?築57年の木造住宅が東京・杉並で倒壊。擁壁が原因か、知られざる危険性とは
2025年10月03日
東京・杉並で発生した築57年の木造住宅倒壊事故は、多くの人々に衝撃を与えました。
その原因として擁壁の劣化が指摘されており、あなたの家にも潜む見えない危険性を示唆しています。
この記事では、事故の真相から、築年数の古い木造住宅や擁壁が抱えるリスクを徹底解説。大
切な命を守るための具体的な点検・対策方法、国や自治体の補助金制度までを網羅的にご紹介します。
あなたの家が安全か、今すぐ確認すべきポイントと、いざという時の備えが分かります。

目次
衝撃のニュース 築57年の木造住宅が東京・杉並で倒壊
杉並区で発生した住宅倒壊事故の概要
東京都杉並区堀ノ内において、先月30日午後7時過ぎ、築57年の木造二階建て住宅が突然倒壊するという衝撃的な事故が発生しました。
杉並区は、この倒壊の主要な原因について、宅地内の土壌の圧力により擁壁(ようへき)に生じていた亀裂が進行した結果、擁壁自体が倒壊に至ったものと推定し、2日に関係各所に発表しました。
この倒壊した住宅は1968年(昭和43年)に建設されたもので、その歴史の中で擁壁の安全性に関する懸念が指摘されていました。
具体的には、1984年の区による調査で擁壁に亀裂があることが判明して以降、杉並区は毎年現地調査を実施し、所有者に対して文書や対面での改善指導を繰り返し行ってきました。
指導の結果、擁壁の亀裂に対するモルタル補修は複数回行われたものの、根本的な安全対策や抜本的な補強工事は実施されないままでした。
さらに、2024年10月の区の現地調査では亀裂が以前よりも広がっていることが確認されたため、杉並区は改めて所有者に対し早期の改善を強く指導するとともに、近隣住民や通行人の安全確保のため、道路に注意喚起のコーンを設置するなどの対応を取っていました。
杉並区は、この擁壁の安全性について、前所有者に8回、現在の所有者には3回にわたり改善指導を行ってきたと説明しています。
事故発生直前の9月24日には、現在の所有者が区役所を訪れ、擁壁の補強工事を行う意向を示していた矢先での崩落事故となりました。
現場の状況と被害報告
住宅倒壊現場では、大量のがれきが散乱し、隣接するマンションのベランダにも一部が流れ込むなど、広範囲にわたる被害が確認されました。
現在もがれき撤去の見通しは立っておらず、復旧には時間を要する状況です。
倒壊した住宅には50代の男性とその20代の息子さんが暮らしていましたが、幸いにも人的被害は免れました。
倒壊当時、家にいた50代の男性は異変を感じて直前に避難し、息子さんは外出中だったため、二人とも無事でした。
この崩落事故を受けて、杉並区は区が把握している擁壁のうち、安全性に問題があるとされる24件について、緊急点検を実施することを決定しました。
これらの擁壁に対し、目視確認や亀裂の計測などを行い、同様の事故の再発防止に向けた対策を急ぐ方針です。
倒壊の原因は擁壁か 専門家が指摘する可能性
擁壁の劣化が引き起こす危険性とは
東京・杉並区で発生した築57年の木造住宅倒壊事故では、擁壁の劣化が主要な原因として指摘されています。
擁壁とは、高低差のある土地において、側面の土砂の崩落を防ぐために設けられる壁状の構造物です。
杉並区は、今回の倒壊について「宅地内の土の圧力により、擁壁に生じていた亀裂が進行したため、擁壁の倒壊に至ったと考えられる」と発表しています。
擁壁に発生した亀裂は、時間の経過とともに進行し、土圧に耐えきれなくなると、最終的に擁壁自体の倒壊、ひいてはその上にある構造物の崩壊を招く危険性があるのです。
今回の事故では、1984年には既に擁壁に亀裂があることが区の調査で判明していました。
その後、複数回にわたるモルタル補修は行われたものの、抜本的な安全対策が講じられることはありませんでした。
表面的な補修だけでは、内部で進行する劣化や構造的な問題に対処できず、見えないところで危険性が増大していく可能性があります。
地盤と老朽化 複合的な要因の検証
築57年という住宅の老朽化と、長年にわたり放置されてきた擁壁の劣化が複合的に絡み合い、今回の倒壊事故に至ったと考えられます。
杉並区は、1968年(昭和43年)に建てられたこの住宅について、1984年の亀裂発見以降、毎年の現地調査に加え、所有者に対して文書や対面での改善指導を継続的に行ってきました。
前所有者には8回、現在の所有者には3回もの指導が行われていたことが明らかになっています。
特に、2024年10月の区の現地調査では亀裂がさらに広がっていることが確認され、区は改めて所有者に早期改善を指導するとともに、近隣住民や通行人への注意喚起として道路にコーンを設置するなどの対応を取っていました。
そして、倒壊直前の2025年9月24日には、現在の所有者が区を訪れ、擁壁の補強工事を行うと話していた矢先に崩落が発生してしまいました。
このような経緯は、老朽化した構造物における危険性の進行が、予想以上に速い場合があることを示唆しています。
杉並区による擁壁に関する指導の経緯を以下に示します。
| 時期 | 主な出来事 | 杉並区の対応 |
|---|---|---|
| 1968年(昭和43年) | 住宅建設 | – |
| 1984年 | 区の調査で擁壁に亀裂が判明 | 所有者への改善指導を開始 |
| 1984年以降 | 亀裂の進行、複数回のモルタル補修 | 毎年の現地調査、文書・対面での指導を継続(前所有者に8回、現所有者に3回) |
| 2024年10月 | 区の現地調査で亀裂の拡大を確認 | 所有者に早期改善を改めて指導、近隣住民・通行人への注意喚起(道路にコーン設置) |
| 2025年9月24日 | 現所有者が区を訪れ、擁壁の補強工事を行うと表明 | – |
| 2025年9月30日 | 住宅倒壊 | がれき撤去の見通し立たず、区が把握する問題のある擁壁24件の緊急点検を開始 |
過去の類似事例から学ぶ教訓
今回の杉並区での住宅倒壊事故は、擁壁の劣化や老朽化が引き起こす潜在的な危険性について、私たちに重要な教訓を与えています。
特に、擁壁に亀裂などの異常が発見された場合、一時的な補修に留まらず、地盤や構造全体を考慮した抜本的な安全対策を早期に講じることの重要性が浮き彫りになりました。
区による度重なる指導があったにもかかわらず、最終的な対策が間に合わなかったことは、危険性の認識と行動の間にギャップがあったことを示唆しています。
また、この事故を受けて杉並区が、区内で把握している安全性に問題がある擁壁24件に対し、目視や亀裂の計測などの緊急点検を実施すると発表したことは、同様のリスクを抱える他の地域や住宅においても、迅速な点検と対策が求められることを示しています。
擁壁の安全性は、その下の地盤の状態や周囲の環境変化によっても影響を受けるため、定期的な専門家による診断と、必要に応じた補修・改修が不可欠です。
幸いにも、今回の事故では、倒壊した住宅にいた50代の男性が異変を感じて直前に避難し、息子も外出中だったため、人的被害は免れました。
しかし、これは偶発的な幸運に過ぎず、常に最悪の事態を想定した予防策と、異常時の迅速な避難行動の準備が、命を守る上でいかに重要であるかを改めて認識させる事例となりました。
あなたの家は大丈夫?築57年以上の木造住宅が抱えるリスク
耐震基準と旧耐震住宅の脆弱性
日本は地震大国であり、住宅の耐震性は命を守る上で極めて重要です。
特に、築57年以上の木造住宅は、現行の耐震基準が導入される以前に建てられた「旧耐震基準」の建物が多く、その脆弱性が指摘されています。
現行の耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日に大幅に改正されました。この改正により、震度6強から7程度の大地震でも倒壊しないことを目標とする「新耐震基準」が定められました。
今回の東京・杉並区で発生した築57年の木造住宅の倒壊事故も、1968年(昭和43年)築であり、旧耐震基準で建てられた建物に該当します。
旧耐震基準の建物は、新耐震基準の建物と比較して、大規模な地震が発生した際に倒壊や損壊のリスクが高いとされています。
これは、建物の構造計算や使用される建材、接合方法などが現在の基準とは異なるためです。
あなたの家が旧耐震基準で建てられている場合、地震に対する備えが不十分である可能性があります。
特に、1981年以前に建てられた木造住宅にお住まいの方は、専門家による耐震診断を受け、必要に応じて耐震改修を検討することが強く推奨されます。
擁壁の安全性をチェックする方法
今回の杉並区の事例では、擁壁の劣化が住宅倒壊の主要な原因とされています。
擁壁は、高低差のある土地で土砂の崩落を防ぐ重要な構造物であり、その安全性が住宅の安定性に直結します。
築年数の古い住宅では、擁壁もまた老朽化が進んでいる可能性が高く、定期的なチェックが不可欠です。
自宅や敷地内の擁壁の安全性を確認するために、以下の点に注意して目視によるチェックを行いましょう。
| チェック項目 | 危険な兆候 |
|---|---|
| 亀裂・ひび割れ | 擁壁の表面に幅0.3mm以上のひび割れや、網の目状の亀裂が見られる場合。特に、水平方向や斜め方向の亀裂は注意が必要です。杉並区の事例でも、擁壁に生じていた亀裂が進行したことが倒壊の原因とされています。 |
| 膨らみ・はらみ出し | 擁壁の一部が外側に膨らんでいたり、はらみ出しているように見える場合。これは内部からの土圧に耐えきれなくなっているサインです。 |
| 傾き・ずれ | 擁壁が垂直ではなく、傾いていたり、隣接する擁壁との間にずれが生じている場合。 |
| 水抜き穴の状況 | 水抜き穴が詰まっている、または水抜き穴から常に水が流れ出ている、あるいは土砂が流出している場合。擁壁内部に水が溜まると土圧が増大し、倒壊のリスクが高まります。 |
| 表面の劣化・剥がれ | コンクリートやモルタルの表面が剥がれていたり、鉄筋が露出している場合。 |
| 植生 | 擁壁の隙間から大きな木の根が入り込んでいる場合。根の成長が擁壁を押し広げ、亀裂を進行させる可能性があります。 |
これらの兆候が見られる場合は、速やかに専門家(建築士、宅地建物取引士、地盤調査会社など)に相談し、詳細な調査と適切な補修・補強工事を検討してください。
杉並区の事例では、擁壁の亀裂に対してモルタル補修は複数回行われたものの、抜本的な安全対策は行われていなかったことが指摘されています。
早期の専門的な対応が、大規模な事故を防ぐ鍵となります。
放置すると危険 危険な兆候を見逃さないで
住宅や擁壁の老朽化による危険な兆候は、初期段階では軽微に見えるかもしれません。
しかし、それらを放置することは、重大な事故につながる可能性を秘めています。
杉並区の倒壊事故のケースでも、擁壁の亀裂は1984年には区の調査で確認されており、その後も区から所有者に対して改善指導が行われていました。
亀裂のモルタル補修は行われたものの、根本的な安全対策が講じられなかった結果、最終的に擁壁の倒壊、そして住宅の崩落に至りました。
特に、旧耐震基準の木造住宅や、古い擁壁が設置されている敷地では、経年劣化によるリスクが常に存在します。
小さなひび割れや、わずかな傾きであっても、地震や豪雨といった外部からの力が加わることで、一気に状況が悪化する可能性があります。
危険な兆候を見逃さず、早期に専門家による診断を受け、適切な対策を講じることが、ご家族の命と財産を守る上で最も重要です。
区はがれき撤去の見通しは立っていないと述べており、このような事態に陥らないためにも、日頃からの注意と調査が求められます。
命を守るための対策と行政の支援
住宅の耐震診断と改修のすすめ
東京・杉並区で発生した築57年の木造住宅倒壊事故は、特に旧耐震基準で建てられた住宅が抱えるリスクを改めて浮き彫りにしました。
1981年(昭和56年)以前に建築された木造住宅は、現在の耐震基準を満たしていない可能性が高く、大規模な地震が発生した場合に倒壊や甚大な損傷のリスクが非常に高まります。
ご自身の住宅が旧耐震基準の建物であるかを確認し、専門家による耐震診断を受けることが、命と財産を守るための第一歩です。
耐震診断では、建物の構造、基礎、地盤の状態、劣化状況などを総合的に評価し、具体的な補強箇所や適切な改修方法が提案されます。
診断結果に基づき、壁の補強、基礎の強化、接合部の金物による補強など、適切な耐震改修を行うことで、地震に対する安全性を大幅に向上させることが可能です。
擁壁の点検と補修の重要性
杉並区の事例では、宅地内の土の圧力により擁壁に生じていた亀裂が進行し、擁壁の倒壊に至ったと考えられています。
この住宅の擁壁には、1984年の区の調査で亀裂が確認されて以来、複数回にわたるモルタル補修は行われたものの、抜本的な安全対策は講じられていませんでした。
擁壁は高低差のある土地で土砂の崩落を防ぐ重要な構造物であり、その安全性が住宅本体だけでなく、周辺の住民や通行人の命にも直結します。
特に築年数の古い擁壁や、長期間にわたり適切なメンテナンスが行われていない擁壁は、地盤からの土圧や雨水の影響により、内部で劣化が進行している可能性があります。
定期的な擁壁の点検は不可欠であり、以下のチェックポイントを参考に、ご自宅や隣接する擁壁に異常がないか確認しましょう。
| チェックポイント | 確認内容 |
|---|---|
| 亀裂の有無と状況 | 擁壁の表面にひび割れや亀裂がないか確認します。特に幅が広く、長さが伸びている亀裂や、複数の亀裂が集中している場合は危険な兆候です。 |
| 変形や傾斜 | 擁壁が外側に膨らんだり、傾いたりしていないか、目視で確認します。わずかな変形でも専門家の診断が必要です。 |
| 水抜き穴の状態 | 水抜き穴が詰まっていないか、水が適切に排出されているかを確認します。水抜きが不十分だと、擁壁内部に水が溜まり土圧が増加します。 |
| 目地や表面の劣化 | コンクリートや石材の目地が剥がれていないか、表面が脆くなったり、欠けたりしていないか確認します。 |
| 擁壁周辺の地盤 | 擁壁の周辺の地盤に沈下や隆起、陥没などが見られないか確認します。 |
杉並区では、今回の事故を受けて、区が把握している安全性に問題がある擁壁24件について緊急点検を実施するとしています。
もし上記の兆候が見られる場合は、速やかに専門家(建築士や土木技術者)に相談し、詳細な調査と適切な補修計画を立てることが重要です。
一時的なモルタル補修だけでなく、根本的な原因を解決する補強工事を検討し、長期的な安全確保に努めましょう。
国や自治体の補助金制度を活用しよう
住宅の耐震診断や改修、擁壁の点検・補修には費用がかかりますが、国や地方自治体では、これらの安全対策を促進するための様々な補助金・助成金制度を設けています。
例えば、多くの自治体では、旧耐震基準の木造住宅を対象とした耐震診断や耐震改修工事に対する補助金制度があります。
また、擁壁の安全対策についても、自治体によっては点検費用や改修工事費用の一部を補助する制度が用意されている場合があります。
これらの制度は、地域や年度によって内容が異なりますので、お住まいの市区町村の窓口や、国土交通省のウェブサイトなどで最新情報を確認することをおすすめします。
補助金を活用することで、経済的な負担を軽減し、より早期に安全対策を実施することが可能になります。
専門家への相談と合わせて、利用可能な補助金制度についても積極的に情報収集を行い、ご自宅の安全確保に役立てましょう。
まとめ
東京・杉並で発生した築57年の木造住宅倒壊事故は、老朽化した擁壁や旧耐震基準の建物が抱える潜在的な危険性を浮き彫りにしました。
この痛ましい事例は、他人事ではありません。あなたの住まいが旧耐震基準の木造住宅であったり、近くに古い擁壁がある場合は、耐震診断や擁壁の専門家による点検を早急に検討することが極めて重要です。
国や自治体による補助金制度も活用し、命と財産を守るための具体的な対策を講じましょう。早期の行動が、将来の安心へと繋がります。