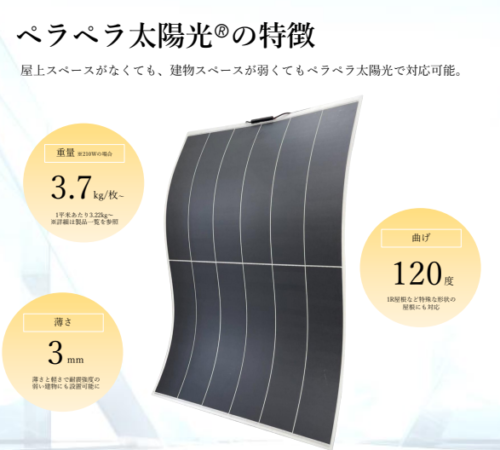宮崎県の注文住宅:土砂災害地域のリスク確認と災害に強い家づくりの対策を徹底解説
2025年09月15日
宮崎県で注文住宅をご検討中の方へ。
豊かな自然に恵まれる宮崎県では、土砂災害のリスクを事前に確認し、適切な対策を講じることが、安心して暮らせるマイホーム実現の鍵となります。
この記事では、宮崎県内の土砂災害地域の確認方法から、土砂災害防止法などの法規制、地盤改良や擁壁、建物構造設計といった災害に強い家づくりの具体的な対策、活用できる補助金制度、そして信頼できるハウスメーカーの選び方まで、宮崎県での安全な家づくりに必要な情報を網羅的に解説します。
後悔しない理想の住まいを手に入れるための第一歩を、この記事から踏み出しましょう。

目次
宮崎県で注文住宅を建てる前に知るべき土砂災害のリスク
宮崎県で理想の注文住宅を建てる際、忘れてはならないのが土砂災害のリスクです。
美しい自然に恵まれた宮崎県ですが、その地理的特性から、土砂災害が発生しやすい地域も少なくありません。
大切な住まいと家族の安全を守るためにも、家を建てる前に土砂災害のリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが極めて重要です。
宮崎県の地理的特徴と土砂災害の現状
宮崎県は九州地方の南東部に位置し、その大部分を九州山地が占めています。
急峻な山々が海岸線近くまで迫る地形が多く、日向灘に面した海岸部には平野が広がっています。
このような地形は、美しい景観を生み出す一方で、土砂災害の発生リスクを高める要因にもなっています。
特に、夏から秋にかけての台風シーズンや梅雨時には、集中豪雨や長雨に見舞われることが多く、これが土砂災害の主要な引き金となります。
過去にも多くの土砂災害が発生しており、宮崎県では土石流、がけ崩れ、地すべりといった様々な形態の土砂災害が発生する可能性があります。
県内各地に土砂災害警戒区域や特別警戒区域が指定されていることからも、そのリスクの高さがうかがえます。
家を建てる土地の選定にあたっては、こうした宮崎県特有の地理的特徴と気象条件を十分に考慮し、土砂災害のリスクを正確に把握することが、安全な住まいづくりの第一歩となります。
土砂災害がもたらす住まいへの影響
土砂災害は、私たちの住まいに甚大な被害をもたらす可能性があります。
その影響は、単に建物が壊れるといった物理的なものにとどまらず、人命に関わる危険性や、生活基盤の喪失、精神的な負担など、多岐にわたります。
主な土砂災害の種類と、それぞれが住まいに与える影響を以下の表にまとめました。
| 土砂災害の種類 | 概要 | 住まいへの主な影響 |
|---|---|---|
| 土石流(どせきりゅう) | 山腹や谷底の土砂や岩石が、集中豪雨などにより大量の水と混じり合い、一気に下流へと流れ下る現象。 |
|
| がけ崩れ(がけくずれ) (急傾斜地の崩壊) |
雨水や地震などにより、急な斜面が突然崩れ落ちる現象。 |
|
| 地すべり(じすべり) | 斜面を構成する地盤の一部が、地下水などの影響で滑り面を境にゆっくりと、あるいは比較的速く移動する現象。 |
|
これらの直接的な被害に加え、土砂災害は以下のような間接的な影響ももたらします。
- 人命の損失や負傷
- 電気、ガス、水道、通信などのライフラインの寸断
- 道路や橋などの交通インフラの破壊による孤立
- 財産の喪失、住宅ローンの残債、再建費用など経済的負担
- 避難生活の長期化や精神的ストレス
- 土地の資産価値の低下
このような深刻な被害を避けるためにも、注文住宅を建てる際には、事前に土砂災害のリスクを十分に確認し、適切な対策を講じることが何よりも重要となります。

宮崎県の土砂災害地域を確認する方法
宮崎県で安心して注文住宅を建てるためには、計画地の土砂災害リスクを正確に把握することが不可欠です。
土砂災害は、台風や集中豪雨など自然災害が多い宮崎県において、住まいと家族の命を守る上で特に重要な要素となります。
ここでは、土砂災害地域を確認するための具体的な方法を詳しく解説します。
ハザードマップを活用した確認手順
ハザードマップは、自然災害による被害が予測される区域や避難場所、避難経路などを地図上に示したもので、住民の避難行動や事前の対策に役立てることを目的としています。
特に土砂災害に関するハザードマップは、土地選びや家づくりの初期段階で必ず確認すべき重要な情報源です。
宮崎県や市町村のハザードマップの入手方法
宮崎県内の土砂災害に関するハザードマップは、主に以下の方法で入手・閲覧することができます。
- インターネットでの閲覧:宮崎県庁のウェブサイトや、各市町村(宮崎市、都城市、延岡市、日向市など)の防災担当部署のウェブサイトで公開されています。多くの場合、デジタルマップとして場所を検索したり、PDF形式でダウンロードしたりすることが可能です。最新の情報が随時更新されているため、定期的な確認をおすすめします。
- 自治体窓口での配布:お住まいになる予定の市町村役場の防災課、危機管理課、または土木・建築関連の部署などで、紙媒体のハザードマップが配布されている場合があります。インターネット環境がない方や、より詳細な説明を受けたい場合は、窓口での相談も有効です。
- 地域説明会など:自治体が開催する防災に関する説明会やイベントなどで、ハザードマップが配布されたり、専門家による解説が行われたりすることもあります。地域の防災意識を高める良い機会にもなります。
ハザードマップの読み解き方と注意点
ハザードマップを入手したら、以下の点に注意して内容を正確に読み解くことが重要です。
- 凡例の確認:マップ上に表示されている色分けや記号が何を意味するのか、必ず凡例を確認しましょう。土砂災害ハザードマップでは、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」や「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」などが色分けで示されています。
- 対象とする災害の種類:ハザードマップには、土砂災害のほか、洪水、津波、高潮など様々な種類があります。注文住宅を検討している土地が、どの種類の災害リスクにさらされているのか、それぞれのマップで確認することが大切です。
- 避難経路と避難場所:万が一の際に備え、自宅から最寄りの指定避難場所までの経路や、危険箇所を事前に確認しておきましょう。複数の避難経路を把握しておくことが望ましいです。
特に土砂災害に関する区域は、以下の2種類に大別され、それぞれ規制内容が異なります。
| 区域の種類 | 概要 | 建築・開発における制限の目安 |
|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) | 土砂災害が発生する恐れがある区域で、住民への情報伝達や避難体制の整備が図られます。 | 特定の建築物に対する直接的な規制はありませんが、自治体によっては開発行為に指導が入る場合があります。土地の形状変更や造成を行う際は、事前の確認が必要です。 |
| 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) | 土砂災害が発生した場合、建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生じる恐れがある区域です。 | 特定の開発行為の制限や、建築物の構造規制(移転勧告、構造規制など)が設けられます。原則として、土砂災害の衝撃に耐えうる構造の建築物でなければ建築できません。 |
ハザードマップはあくまで予測情報であり、記載されていない場所でも災害が発生する可能性はゼロではありません。
また、土地の造成や開発などによって状況が変化することもあります。
常に最新の情報を確認し、周辺の地形や環境も総合的に判断することが重要です。
自治体の窓口や専門家への相談
ハザードマップで大まかなリスクを把握した後は、より詳細な情報を得るために、自治体の窓口や専門家へ相談することをおすすめします。
宮崎県の土砂災害に関する担当部署
宮崎県庁や各市町村役場には、土砂災害に関する情報提供や相談を受け付けている部署があります。
- 宮崎県庁の担当部署:宮崎県土整備部砂防課や、各土木事務所などが、土砂災害防止法に基づく区域指定や砂防施設に関する情報を持っています。具体的な土地の状況や規制について、専門的な見地からの説明を受けることができます。
- 市町村役場の担当部署:各市町村の防災課、危機管理課、建築指導課、都市計画課などが、ハザードマップの詳細な説明や、地域の防災計画、建築に関する条例、開発許可の基準などについて情報提供を行っています。また、土砂災害対策に関する補助金制度など、具体的な支援策についても相談できる場合があります。
相談する際は、検討している土地の正確な所在地(地番)を伝え、どのような情報を知りたいのか具体的に質問できるよう準備しておきましょう。
宅地建物取引業者や建築士への相談のすすめ
土地の購入や注文住宅の建築を検討する際には、専門知識を持つ宅地建物取引業者や建築士に相談することが非常に有効です。
- 宅地建物取引業者:土地の売買を仲介する宅地建物取引業者は、重要事項説明の際に、土砂災害警戒区域などの法的規制について説明する義務があります。地域の土地情報に精通しているため、ハザードマップの情報と合わせて、より安全な土地を探す上でのアドバイスを得られるでしょう。土砂災害リスクを考慮した土地探しを依頼する際は、その実績や知見を確認することが重要です。
- 建築士:建築士は、土地の状況や法規制を踏まえ、安全かつ適切な建物の設計を行う専門家です。土砂災害特別警戒区域内で建築する際の構造上の要件や、地盤改良の必要性、擁壁の設置など、具体的な対策について専門的なアドバイスを受けることができます。特に、土砂災害対策の実績が豊富な建築士を選ぶことで、より安心できる家づくりが実現します。
これらの専門家は、ハザードマップだけではわからない、より詳細な地盤情報や過去の災害履歴、周辺の地形変化なども考慮に入れた総合的な判断をサポートしてくれます。
複数の専門家から意見を聞く「セカンドオピニオン」も、後悔しない家づくりのためには有効な手段です。

土砂災害地域における注文住宅建築の法規制と可能性
宮崎県で注文住宅を計画する際、土砂災害の危険性が指摘される地域では、特別な法規制と建築上の配慮が必要となります。
安全な住まいを実現するためには、これらの法規制を正確に理解し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。
土砂災害防止法とは何か
「土砂災害防止法」は、正式には「土砂災害警戒区域等における土砂災害対策の推進に関する法律」といい、土砂災害から国民の生命・身体を保護することを目的としています。
土砂災害が発生するおそれのある区域を「土砂災害警戒区域」に指定し、その中で特に著しい被害が生じるおそれのある区域を「土砂災害特別警戒区域」に指定することで、対策を推進するものです。
宮崎県は急峻な山間部や河川沿いの地域が多く、過去にも土砂災害が発生しているため、この法律に基づく対策は非常に重要となります。
土砂災害警戒区域と特別警戒区域の違い
土砂災害防止法では、土砂災害の危険度に応じて二種類の区域が指定されています。
それぞれの区域には異なる規制が設けられており、注文住宅を建てる際には、自身の計画地がどちらの区域に該当するかを正確に把握することが重要です。
| 区域の名称 | 通称 | 指定の基準 | 主な規制内容 |
|---|---|---|---|
| 土砂災害警戒区域 | イエローゾーン | 土砂災害が発生した場合に、住民の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域。 |
|
| 土砂災害特別警戒区域 | レッドゾーン | 土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民の生命または身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域。 |
|
これらの区域は、宮崎県や各市町村が公開しているハザードマップで確認することができます。
ご自身の土地がどちらの区域に該当するかによって、家づくりの計画や必要な対策が大きく変わるため、必ず事前に確認しましょう。
建築基準法による制限と許可
土砂災害警戒区域や特別警戒区域内で注文住宅を建てる場合、土砂災害防止法だけでなく、「建築基準法」による制限も受けます。
建築基準法は、建物の敷地、構造、設備、用途に関する最低限の基準を定めており、国民の生命、健康、財産の保護を目的としています。
特に土砂災害特別警戒区域では、建築基準法に基づき、建築物の構造についてより厳しい基準が適用されます。
具体的には、土砂の衝撃に耐えうる強固な基礎構造や壁の強度などが求められることがあります。
これは、土砂災害が発生した際に建物が倒壊したり、土砂が流入して居住者に危害が及ぶことを防ぐためです。
建築確認申請の際には、これらの法規制に適合していることを示す詳細な設計図や構造計算書などの提出が義務付けられます。
場合によっては、特別な許可や認定が必要となることもあります。専門知識を持つ建築士と連携し、法令遵守を徹底することが重要です。
土砂災害地域でも注文住宅は建てられるのか
「土砂災害地域だから注文住宅は建てられない」と一概に諦める必要はありません。
結論から言えば、多くのケースで注文住宅を建てることは可能です。
ただし、通常の土地に比べて、より詳細な調査、専門的な設計、そして特別な対策が必要となり、それに応じたコストも発生することを理解しておく必要があります。
特に土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)においては、建築基準法に基づく構造規制が適用されるため、建物の構造や基礎に高い強度が求められます。
例えば、鉄筋コンクリート造の擁壁の設置、地盤改良工事、建物の基礎を深くするなどの対策が考えられます。
これらの対策を適切に行うことで、土砂災害に対する安全性を確保し、建築許可を得ることが可能になります。
しかし、非常に危険度の高い場所や、対策が物理的・経済的に困難な場所では、建築が認められないケースや、事実上不可能となるケースも存在します。
そのため、土地の購入前や計画の初期段階で、必ず自治体の担当部署や専門家(建築士、宅地建物取引業者、地盤調査会社など)に相談し、その土地の具体的なリスクと建築の可能性、必要な対策、そしてそれにかかる費用について、詳細な情報を得るようにしましょう。
安全性を最優先に考え、後悔のない家づくりを進めることが何よりも大切です。

災害に強い宮崎県の注文住宅を建てるための対策
宮崎県で土砂災害のリスクがある地域において、安心して暮らせる注文住宅を建てるためには、多角的な視点からの対策が不可欠です。
土地選びの初期段階から、地盤、基礎、そして建物の構造や設計に至るまで、それぞれの工程で適切な対策を講じることで、災害に強い家づくりを実現できます。
土地選びの段階で考えるべきこと
注文住宅の災害対策は、家を建てる土地を選ぶ段階から始まります。
安全な土地を見極めること、そしてその土地の地盤状況を正確に把握することが、その後の対策の基礎となります。
より安全な土地を見極めるポイント
ハザードマップの確認はもちろん重要ですが、それだけに頼らず、現地での確認や過去の災害履歴の調査も合わせて行うことで、より安全な土地を見極めることができます。
- 地形と傾斜の確認: 崖の直下や急傾斜地、谷間、沢筋などは土砂災害のリスクが高い傾向にあります。平坦な土地でも、周辺の山や崖の状況を確認しましょう。
- 過去の災害履歴の調査: その土地や周辺地域で過去に土砂崩れや浸水などの災害が発生していないか、自治体の防災担当部署や地域の古老、不動産会社に確認することが有効です。
- 周辺の治水施設の確認: 砂防ダムや擁壁、排水溝などの治水施設が適切に整備されているか、またその施設の老朽化状況も確認しましょう。
- 地質情報の確認: 地質図やボーリングデータなど、専門的な地質情報を確認できる場合は、軟弱地盤や不安定な地層がないか確認します。
- 周辺の状況変化: 過去に大規模な造成が行われた土地や、周辺で大規模な開発が進んでいる場合は、地盤の安定性に影響を与える可能性も考慮します。

地盤調査の重要性と内容
土地の地盤状況は、見ただけでは判断できません。
建物を安全に支えるためには、専門的な地盤調査が不可欠です。
地盤調査によって、軟弱地盤の有無や液状化のリスクなどを正確に把握し、適切な基礎構造や地盤改良の必要性を判断します。
主な地盤調査の種類と特徴は以下の通りです。
| 調査方法 | 概要 | 特徴 |
|---|---|---|
| スウェーデン式サウンディング試験 | ロッドの先端にスクリューポイントを取り付け、荷重をかけながら回転させて地中に貫入させ、その抵抗値から地盤の硬さを測定します。 | 比較的費用が安く、小規模な住宅建築で広く用いられます。軟弱地盤の深度や硬さを把握するのに適しています。 |
| ボーリング調査 | 地盤に穴を掘り、地中の土を採取して地質や土の強度を詳細に調べます。地下水位の測定も可能です。 | 大規模建築物や複雑な地盤状況の場所で用いられます。地盤の状況を最も正確に把握できますが、費用は高めです。 |
| 表面波探査 | 地表面に人工的な振動を与え、その振動波の伝わり方から地盤の硬さや構造を非破壊で調査します。 | 地盤を傷つけずに広範囲の地盤状況を把握できます。液状化の可能性の判断にも有効です。 |
これらの調査結果に基づいて、地盤の許容支持力や沈下量、液状化の可能性などを評価し、最適な基礎設計や地盤改良計画を策定します。
地盤と基礎を強化する対策
地盤調査の結果、地盤に問題があると判断された場合や、より安全性を高めたい場合には、地盤改良工事や強固な基礎構造の採用が重要になります。
強固な基礎構造の種類と特徴
建物の荷重を地盤に伝える基礎は、家を支える最も重要な部分です。
土砂災害地域では、特に強固で安定した基礎構造を選ぶことが求められます。
| 基礎の種類 | 概要 | 特徴と土砂災害対策におけるメリット |
|---|---|---|
| ベタ基礎 | 建物の底面全体を鉄筋コンクリートで覆う面状の基礎です。 | 建物の荷重を広範囲に分散させるため、不同沈下を起こしにくい特徴があります。地面からの湿気やシロアリの侵入も防ぎやすく、土砂災害による液状化や地盤沈下に対しても比較的強いとされています。 |
| 布基礎 | 建物の壁の下に沿って逆T字型の鉄筋コンクリートを連続して設ける基礎です。 | ベタ基礎に比べて使用するコンクリート量が少なく、コストを抑えられます。ただし、地盤の弱い場所や不同沈下のリスクが高い場所では、ベタ基礎の方が推奨されることが多いです。 |
| 杭基礎 | 地盤の深い部分にある支持層まで杭を打ち込み、その杭で建物を支える基礎です。 | 非常に軟弱な地盤や、建物の重量が大きい場合に採用されます。土砂災害による地盤の流動化や沈下に対して高い抵抗力を持ちますが、費用は高額になります。 |
宮崎県の土砂災害地域では、特にベタ基礎や杭基礎の採用を検討し、地盤状況に応じた最適な基礎構造を選定することが重要です。
地盤改良工事の必要性と工法
地盤調査の結果、地盤が軟弱であると判断された場合や、液状化のリスクが高いとされた場合には、地盤改良工事が必要となります。
地盤改良は、地盤の強度を高め、建物の沈下や傾斜を防ぐための重要な対策です。
| 工法の種類 | 概要 | 適用地盤と特徴 |
|---|---|---|
| 表層改良工法 | 地表から約2m程度の深さまでの軟弱地盤を掘削し、セメント系固化材を混ぜて締め固めることで地盤を強化します。 | 比較的浅い部分の軟弱地盤に適用されます。費用も比較的安価ですが、深い部分の軟弱地盤には不向きです。 |
| 柱状改良工法 | 地中に柱状の穴を掘り、セメント系固化材と土を混ぜて円柱状の改良体を形成し、建物をその改良体で支えます。 | 地表から約2m~8m程度の深さの軟弱地盤に適用されます。液状化対策としても有効な場合があります。 |
| 鋼管杭工法 | 鋼製の杭を地盤の支持層まで打ち込み、その杭で建物を支えます。 | 非常に軟弱な地盤や、深い位置に支持層がある場合に適用されます。大きな建物の荷重にも対応でき、液状化対策としても非常に効果的です。費用は高額になります。 |
これらの工法は、地盤の状況や建物の規模、予算に応じて最適なものが選ばれます。
専門家と十分に相談し、適切な地盤改良計画を立てることが重要です。
擁壁や排水設備による対策
敷地全体を土砂災害から守るためには、建物の基礎だけでなく、敷地外周や敷地内の適切な擁壁の設置と、効果的な排水設備の計画が不可欠です。
適切な擁壁の設置とメンテナンス
敷地に高低差がある場合や、隣接する斜面がある場合には、擁壁(ようへき)の設置が土砂災害対策として非常に重要です。
擁壁は土の圧力に耐え、地盤の崩壊を防ぐ役割を担います。
- 擁壁の種類と選定: 擁壁には、重力式擁壁、L型擁壁、逆T型擁壁など様々な種類があり、地盤の状況や高さ、土の圧力に応じて適切な構造を選定する必要があります。専門家による構造計算に基づいた設計が必須です。
- 水抜き穴の設置: 擁壁の裏側に水が溜まると、土圧が増大し擁壁の崩壊につながる可能性があります。適切な位置に水抜き穴を設置し、擁壁内部の水を排出する仕組みが重要です。
- 定期的な点検と補修: 擁壁は経年劣化や地震などによってひび割れや傾斜が生じることがあります。定期的に点検を行い、異常が見られた場合は速やかに専門家による補修を行うことが大切です。
- 建築基準法と土砂災害防止法の遵守: 擁壁の高さや構造には、建築基準法や土砂災害防止法に基づく規制があります。これらの法令を遵守した設計・施工が求められます。
敷地内の効果的な排水計画
敷地内の水はけが悪いと、地盤が軟弱化したり、雨水が建物の基礎に侵入したりして、土砂災害のリスクを高める可能性があります。
効果的な排水計画は、敷地を乾燥した状態に保ち、地盤の安定性を維持するために重要です。
- 敷地全体の勾配設計: 敷地全体を緩やかな勾配に設計し、雨水が自然に低い方向へ流れ、敷地外へ排出されるように計画します。建物周辺に水が溜まらないように配慮が必要です。
- 雨水浸透ますや側溝の設置: 敷地内の雨水を効率的に集め、地下に浸透させる雨水浸透ますや、敷地外へ排水する側溝、U字溝などを適切に配置します。
- 透水性舗装の活用: 駐車場やアプローチなど、舗装が必要な場所には透水性のある素材を使用することで、雨水の地中への浸透を促し、表面水の量を減らすことができます。
- 貯留槽の設置: 大量の雨水を一時的に貯留し、ゆっくりと排水する貯留槽の設置も、集中豪雨時の浸水対策として有効です。
- 定期的な清掃とメンテナンス: 排水溝や雨水ますに落ち葉や泥が詰まると、排水機能が低下します。定期的な清掃とメンテナンスを心がけましょう。
建物の構造や設計でできる対策
土地選びや地盤・基礎の対策と並行して、建物自体の構造や設計においても、土砂災害に強い家づくりを目指すための工夫が求められます。
耐震性・耐風性を高める設計
土砂災害は地震や豪雨と密接に関連しています。
そのため、建物自体が高い耐震性と耐風性を持つことは、間接的に土砂災害に対する抵抗力を高めることにも繋がります。
- 耐震等級の確保: 建築基準法で定められた最低限の耐震性能(耐震等級1)に加え、より高い耐震等級(耐震等級2や3)を目指すことで、地震に対する安全性を高めます。耐震等級3は、数百年に一度の大地震にも耐えうるレベルとされています。
- 制震・免震構造の採用: 地震の揺れを吸収・軽減する制震装置や、建物と基礎を分離して揺れを伝わりにくくする免震装置の導入も、建物の安全性を大幅に向上させます。
- 壁量計算と構造計算: 建築基準法に基づいた壁量計算に加え、より詳細な構造計算(許容応力度計算や保有水平耐力計算)を行うことで、建物の強度とバランスを精密に検証します。
- 屋根材の軽量化: 屋根材を軽量化することで、建物の重心が下がり、地震や強風時の揺れを軽減できます。
- 開口部の配置と補強: 窓やドアなどの開口部は、耐力壁としての機能が弱まるため、適切な配置と補強(まぐさ、窓台の強化など)が必要です。強風に対する飛散防止対策も重要です。
- 外壁材の選定: 衝撃に強く、防水性の高い外壁材を選ぶことで、土砂や水の侵入を防ぎ、建物の劣化を抑えます。
避難経路や避難場所を考慮した配置
万が一、土砂災害が発生した場合に備え、迅速かつ安全に避難できるような建物の配置や設計も重要です。
- 高基礎の採用: 土砂災害警戒区域や浸水想定区域では、建物の基礎を通常よりも高くする「高基礎」を採用することで、土砂や水の侵入を遅らせ、避難時間を確保できます。
- 2階リビングや避難スペースの確保: 1階部分が土砂や水に浸かるリスクがある場合、2階に主要な生活空間(リビング、寝室など)を設けることで、一時的な避難場所を確保できます。
- 複数の避難経路の確保: 災害時に一つの経路が使えなくなる可能性を考慮し、建物から敷地外へ、または敷地内のより安全な場所へ避難するための複数の経路を確保します。
- 周辺の避難場所へのアクセス: 自治体が指定する避難場所までの経路や距離を確認し、そこへ安全にたどり着けるような敷地配置や経路計画を検討します。
- 開口部の位置と強度: 避難経路となる窓やドアは、非常時に開けやすく、かつ土砂や水圧に耐えうる強度を持つことが望ましいです。

土砂災害対策に関する支援制度と補助金
宮崎県で土砂災害に強い注文住宅を建てる際、気になるのがその費用です。
しかし、国や宮崎県、各市町村では、土砂災害対策を促進するための様々な支援制度や補助金、融資制度が用意されています。
これらの制度を上手に活用することで、費用負担を軽減し、より安全な住まいづくりを実現できます。
国や宮崎県の補助金制度
土砂災害対策に関する補助金制度は、国が主導するものと、各地方自治体が独自に設けるものがあります。
これらの制度は、住民の安全確保と地域防災力の向上を目的としています。
国の主な支援制度
国が主導する土砂災害対策の支援制度は、地方公共団体を通じて実施されることが一般的です。
特に、生命の安全に直結する危険性の高い住宅への支援が重点的に行われています。
| 制度名 | 概要 | 対象となる対策例 |
|---|---|---|
| がけ地近接等危険住宅移転事業 | 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)や、それに準ずる危険な場所に建つ住宅からの移転を支援する制度です。危険な場所からの避難・移転を促進し、生命の安全を確保することを目的としています。 |
|
| 土砂災害対策関連事業(地方公共団体向け) | 国が地方公共団体に対して交付金を支給し、地方公共団体が土砂災害防止施設(砂防ダム、擁壁など)の整備やハザードマップ作成などの事業を実施することを支援します。間接的に住民の安全に寄与します。 |
|
これらの制度の詳細は、各地方公共団体の窓口で確認することが重要です。
特に「がけ地近接等危険住宅移転事業」は、宮崎県内の各市町村でも実施されており、移転を検討する際の大きな支えとなります。
宮崎県・市町村の補助金制度
宮崎県や各市町村では、国の制度に加え、地域の実情に応じた独自の補助金制度を設けている場合があります。
これらは、土砂災害対策工事や防災改修を促進するためのものです。
具体的な補助金制度は、各市町村によって内容や要件が大きく異なるため、必ずお住まいの、または建築予定地の市町村役場の防災担当課や建築指導課に直接問い合わせて確認してください。
- 土砂災害対策工事費補助金: 危険ながけ地への擁壁設置や補強、地盤改良工事など、直接的な土砂災害対策工事にかかる費用の一部を補助する制度です。
- 防災改修費補助金: 既存住宅の耐震改修や防災機能向上改修など、間接的に土砂災害への備えとなる改修工事を支援する制度です。
- 移転促進補助金: 国のがけ地近接等危険住宅移転事業と連携し、さらに手厚い支援を行う市町村もあります。
これらの補助金は、予算に限りがあるため、申請期間や要件を事前に確認し、計画的に申請することが大切です。
融資制度や税制優遇の活用
補助金だけでなく、土砂災害対策に関連する融資制度や税制優遇措置も活用することで、経済的な負担をさらに軽減できます。
災害対策に利用可能な融資制度
土砂災害対策工事や、安全な土地への移転・新築にかかる費用に対して、低利で融資を受けられる制度があります。
- 地方公共団体による低利融資: 宮崎県や各市町村が、防災対策工事や危険住宅からの移転費用に対して、独自の低利融資制度を設けている場合があります。詳細は各自治体の窓口で確認が必要です。
- 住宅金融支援機構の融資制度: 直接的な土砂災害対策に特化した融資は少ないですが、例えば「フラット35」において、省エネルギー性や耐久性・可変性などに優れた「長期優良住宅」を建設する場合には、金利の優遇が受けられます。長期優良住宅は、防災性能も一定水準以上であることが求められるため、間接的に土砂災害に強い家づくりを支援する形となります。
- 民間金融機関の防災関連ローン: 一部の民間金融機関では、耐震改修や防災対策工事に特化したリフォームローンや、住宅ローンの中で防災性能向上を評価する商品を提供している場合があります。
融資制度は、補助金と異なり返済が必要ですが、低金利で長期にわたる返済計画を立てられるため、一時的な費用負担を抑える有効な手段となります。
税制上の優遇措置
住宅の取得や改修にかかる税金についても、特定の条件を満たすことで優遇措置が適用される場合があります。
土砂災害対策工事が直接的な減税対象となるケースは稀ですが、関連する制度を活用できる可能性があります。
- 住宅ローン減税: 住宅ローンを利用して新築やリフォームを行う場合、所得税や住民税から一定額が控除される制度です。長期優良住宅や低炭素住宅など、特定の性能基準を満たす住宅は、控除額が優遇される場合があります。これらの住宅は、防災性能も考慮されているため、結果的に土砂災害に強い家づくりが税制面からも支援されます。
- リフォーム減税: 特定のバリアフリー改修、省エネ改修、耐震改修などを行った場合に、所得税の控除や固定資産税の減額が受けられる制度です。土砂災害対策として行う擁壁の補強や地盤改良工事などが、これらの改修と複合的に行われる場合、対象となる可能性がないか確認してみましょう。
- 固定資産税の減免: 災害により住宅が被害を受けた場合に、その後の復旧や再建に対して固定資産税が減免される制度はありますが、土砂災害の予防対策工事そのものに対する固定資産税の減免は限定的です。ただし、長期優良住宅の認定を受けた新築住宅は、一定期間固定資産税が軽減される優遇措置があります。
税制優遇措置は、所得や工事内容、住宅の性能などによって適用条件が細かく定められています。
税務署や税理士、またはお住まいの市町村の税務担当課に相談し、ご自身のケースで利用できる制度があるか確認することをおすすめします。

後悔しないためのハウスメーカー・工務店の選び方
宮崎県で土砂災害のリスクがある地域に注文住宅を建てる際、最も重要な要素の一つが、信頼できるハウスメーカーや工務店選びです。
一般的な住宅建築とは異なり、土砂災害対策には専門的な知識と経験が不可欠となります。
後悔のない家づくりを実現するためにも、以下のポイントを参考に、慎重に業者を選びましょう。
土砂災害対策の実績が豊富な業者を選ぶ
土砂災害対策は、地盤の状況、地域の特性、法規制など、多岐にわたる専門知識を要します。
そのため、単に「家を建てる」だけでなく、「災害に強い家を建てる」という視点を持つ業者を選ぶことが極めて重要です。
具体的には、以下のような点を業者選定の基準とすることをおすすめします。
- 過去に土砂災害警戒区域や特別警戒区域での施工実績があるか
- 地盤改良や擁壁工事、排水計画など、土砂災害対策に関する具体的な施工事例を提示できるか
- 土木工学や地盤工学、防災工学などの専門知識を持つスタッフが在籍しているか
- 地域の地質や過去の災害事例に関する深い理解があるか
- 自治体の土砂災害に関する法規制や補助金制度に精通しているか
これらの実績や専門性は、業者のウェブサイトやパンフレットだけでなく、直接面談して質問することで確認できます。
具体的な事例や対策方法について、納得のいく説明が得られるかどうかが、信頼できる業者を見極めるポイントとなるでしょう。
業者選定の際には、以下のチェックリストも参考にしてください。
| 確認項目 | 詳細 |
|---|---|
| 施工実績 | 土砂災害警戒区域・特別警戒区域内での建築実績の有無、具体的な対策事例 |
| 専門知識 | 地盤工学・防災工学などの専門家が在籍しているか、技術研修の実施状況 |
| 法規制への理解 | 土砂災害防止法、建築基準法、自治体条例などへの精通度 |
| 提案力 | 土地の状況に応じた最適な地盤改良・基礎構造・擁壁・排水計画の提案 |
| アフターサービス | 引き渡し後の定期点検、災害時の緊急対応体制 |
地盤調査から設計、施工まで一貫した対応
土砂災害対策を伴う注文住宅の建築では、地盤調査から設計、そして実際の施工に至るまで、一貫した体制で対応できる業者を選ぶことが非常に重要です。
各工程が分断されていると、情報伝達のミスや責任の所在が不明確になるリスクがあり、結果として対策の不備につながる可能性があります。
一貫対応のメリットは以下の通りです。
- 情報共有の円滑化: 地盤調査で得られた詳細なデータが、設計者から施工者へとスムーズに伝わり、最適な対策が講じられます。
- 責任の明確化: 建築プロセス全体にわたる責任を一つの業者が負うため、万が一問題が発生した場合でも、迅速かつ的確な対応が期待できます。
- コストパフォーマンス: 各工程を個別の業者に依頼するよりも、全体としてコストを抑えられる場合があります。
- 品質の安定: 設計者の意図が施工に正確に反映されやすいため、計画通りの高い品質が確保されます。
特に地盤調査は、土砂災害対策の出発点であり、その結果に基づいて適切な基礎構造や地盤改良工法が決定されます。
この重要な工程を自社または信頼できる提携機関で行い、その結果を設計・施工に密接に連携させられる業者を選びましょう。
契約前に、地盤調査から引き渡しまでの具体的な流れと、各工程での連携体制について詳しく確認することが大切です。
地域密着型業者のメリット
宮崎県で注文住宅を建てる場合、特に土砂災害対策を考慮するなら、地域密着型のハウスメーカーや工務店を選ぶことには大きなメリットがあります。
地域密着型業者は、長年にわたりその地域で事業を行っているため、以下のような点で強みを持っています。
- 地域の特性への深い理解: 宮崎県特有の気候(台風など)、地質、過去の災害履歴に関する豊富な知識と経験を持っています。これにより、その土地に最適な土砂災害対策を提案できる可能性が高いです。
- 地元の法規制や制度への精通: 国の法律だけでなく、宮崎県や各市町村独自の条例、補助金制度、手続きなどに詳しく、スムーズな家づくりをサポートしてくれます。
- 協力業者との連携: 地元の信頼できる地盤調査会社、基礎工事業者、擁壁工事業者などと強固なネットワークを築いていることが多く、高品質な施工が期待できます。
- 迅速なアフターサービス: 地域内に拠点があるため、引き渡し後のメンテナンスや、万が一の災害時にも迅速に対応してもらいやすいという安心感があります。
- 口コミや評判の確認: 地元での実績が多いため、実際にその業者で家を建てた人の生の声や評判を収集しやすく、信頼性を判断する上で貴重な情報源となります。
地域密着型業者を選ぶ際は、宮崎県内での施工実績数や、地元の住民からの評判、アフターサービス体制などを重点的に確認し、安心して任せられるパートナーを見つけることが成功の鍵となります。

まとめ
宮崎県で注文住宅を建てる際、土砂災害リスクの確認と対策は不可欠です。
ハザードマップでの現状把握、自治体や専門家への相談を通じて、法規制や建築可能性を正確に理解しましょう。
土地選びから地盤・基礎強化、擁壁・排水設備、建物の耐震・耐風設計まで、多角的な対策が重要です。
国や宮崎県の支援制度も活用し、土砂災害対策に実績豊富なハウスメーカー・工務店を選ぶことで、安心で安全な住まいが実現します。
これらの徹底した準備と対策により、土砂災害地域でも後悔のない理想の注文住宅を建てることが可能です。