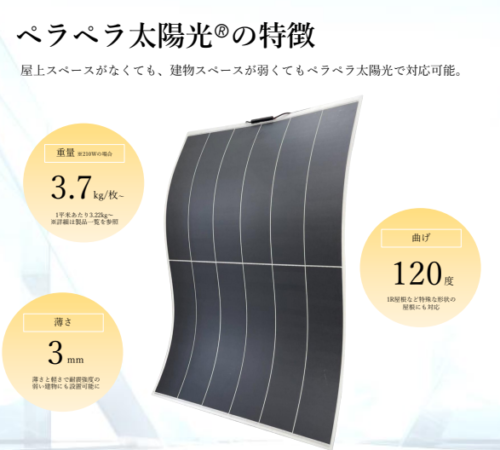【最新】宮﨑県の線状降水帯による危険を回避!災害に備える万全の防災対策
2025年08月22日
宮﨑県で線状降水帯が発生すると、洪水や土砂災害、浸水など甚大な被害をもたらす危険があります。
宮﨑県が線状降水帯の影響を受けやすい地理的要因と、それによる具体的な危険性を解説します。
この記事では、宮﨑県にお住まいの方や関係者に向けて、線状降水帯から命を守るための万全な防災対策を徹底解説します。
ハザードマップの確認から避難行動、備蓄品、そして災害後の情報収集まで、あなたの命と安全を守るための具体的な知識と行動が全て分かります。
大切な家族と地域を守るために、万全の防災対策が不可欠です。

目次
- 1 はじめに 宮﨑県で線状降水帯が発生したら
- 2 宮﨑県における線状降水帯の具体的な危険性
- 3 線状降水帯に備える万全の防災対策 事前準備編
- 3.1 ハザードマップを確認する 危険箇所と避難経路の把握
- 3.2 確認すべきハザードマップの種類
- 3.3 自宅や周辺地域の危険度を把握する
- 3.4 ハザードマップの入手方法と活用
- 3.5 避難場所と避難経路の確認 宮﨑県内の指定避難所情報
- 3.6 指定避難所の種類と確認ポイント
- 3.7 安全な避難経路の確認とシミュレーション
- 3.8 非常持ち出し袋の準備と備蓄品の確認
- 3.9 非常持ち出し袋(一次持ち出し品)の準備
- 3.10 備蓄品(二次持ち出し品・自宅避難用)の確認
- 3.11 定期的な点検と見直し
- 3.12 家族との連絡手段と安否確認方法の共有
- 3.13 災害用伝言サービスを活用する
- 3.14 安否確認方法と集合場所の共有
- 3.15 防災情報の入手方法と活用 気象庁や自治体の情報源
- 3.16 気象庁からの情報
- 3.17 宮崎県および市町村からの情報
- 3.18 テレビ・ラジオ・携帯電話の緊急速報
- 3.19 防災アプリの活用
- 4 線状降水帯発生中の命を守る行動 危険を回避する対策
- 5 線状降水帯通過後の行動と復旧支援
- 6 まとめ
はじめに 宮﨑県で線状降水帯が発生したら
宮﨑県にお住まいの皆様、または宮﨑県への訪問を予定されている皆様にとって、近年頻発する線状降水帯は決して他人事ではありません。
線状降水帯は、短時間で局地的に記録的な大雨をもたらし、甚大な災害を引き起こす可能性を秘めています。
この章では、線状降水帯の基本的な知識と、なぜ宮﨑県で特に警戒が必要なのかを解説し、来るべき災害に備える第一歩とします。
線状降水帯とは何か その危険性を知る
線状降水帯とは、発達した積乱雲が次々と発生し、同じ場所を通過または停滞することで、線状に連なって大雨を降らせる現象です。
気象庁は、この現象を「線状の降水域が数時間にわたって停滞し、その領域内で強い降水を伴う積乱雲が次々と発生・通過することで、非常に激しい雨が降り続く現象」と定義しています。
その最大の特徴は、短時間で極めて大量の雨が狭い範囲に集中することにあります。
これにより、通常では考えられないような急激な河川の水位上昇や土砂の流出が発生し、生命や財産に深刻な被害をもたらす危険性が高まります。
線状降水帯が発生すると、数時間で平年の月降水量を超えるような雨が降ることもあり、広範囲にわたる洪水、土砂災害、浸水被害を引き起こすリスクが非常に高まります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 発達した積乱雲が線状に連なり、同じ場所で長時間大雨を降らせる現象 |
| 特徴 | 数時間にわたり、極めて強い雨が狭い範囲に集中して降る |
| 危険性 | 急激な河川の増水・氾濫、土砂災害、広範囲の浸水被害を引き起こす |
なぜ宮﨑県で線状降水帯が危険なのか 地理的要因と過去の事例
宮﨑県は、その地理的特性から線状降水帯による豪雨災害のリスクが高い地域の一つです。
県土の約76%を山地が占め、急峻な地形が多いことに加え、太平洋に面しているため、気象条件が重なると線状降水帯が発生しやすくなります。
特に、梅雨末期や台風シーズンには、太平洋からの暖かく湿った空気が九州山地にぶつかり上昇することで積乱雲が発達しやすくなります。
この気流が長時間停滞したり、次々と流れ込んだりすることで、線状降水帯が形成され、同じ地域に記録的な大雨をもたらす可能性が高まります。
山間部で降った雨が短時間で河川に集中し、下流域で急激な増水や氾濫を引き起こすことも懸念されます。
過去には、宮﨑県内においても線状降水帯が原因とみられる集中豪雨により、河川の氾濫や土砂災害、大規模な浸水被害が発生し、甚大な被害を経験してきました。
これらの事例は、宮﨑県が線状降水帯に対して特に警戒が必要な地域であることを示しており、住民一人ひとりが防災意識を高め、適切な対策を講じることが不可欠です。

| 要因 | 宮﨑県における影響 |
|---|---|
| 地理的要因 | 県土の約76%が山地であり、急峻な地形が多い。太平洋に面し、湿った空気が流れ込みやすい。 |
| 気象条件 | 梅雨末期や台風シーズンに、太平洋からの暖湿気流が九州山地にぶつかり積乱雲が発達しやすい。 |
| 過去の事例 | 線状降水帯が原因とみられる集中豪雨により、河川氾濫、土砂災害、浸水被害が度々発生している。 |
宮﨑県における線状降水帯の具体的な危険性
線状降水帯は、積乱雲が次々と発生し、同じ場所を通過することで、数時間にわたって非常に強い雨が降り続く現象です。
宮﨑県では、その地理的特性や過去の気象災害の履歴から、線状降水帯が発生した場合に特に深刻な危険性が高まります。ここでは、宮﨑県が直面する具体的な災害リスクについて詳しく解説します。
洪水や河川氾濫の危険 宮﨑県の主要河川と注意点
宮﨑県は、九州山地を源流とする多くの河川が流れ、日向灘へと注ぎます。
線状降水帯による短時間での集中豪雨は、これらの河川の水位を急激に上昇させ、洪水や氾濫を引き起こす可能性が非常に高まります。
特に、平野部を流れる主要な河川では、一度氾濫すると広範囲にわたる浸水被害が発生し、甚大な被害をもたらすことがあります。
宮﨑県の主要河川と線状降水帯によるリスク
宮﨑県内には、大淀川、五ヶ瀬川、小丸川、耳川、一ツ瀬川といった主要な河川があり、それぞれ異なる特性と危険性を持ちます。
線状降水帯による豪雨は、これらの河川の流域全体に影響を及ぼし、予測困難な急激な増水や堤防の決壊、越水を引き起こすことがあります。
| 河川名 | 主な流域 | 線状降水帯による危険性 |
|---|---|---|
| 大淀川 | 都城市、宮崎市など | 県内最大の河川で、下流域の市街地や低地での大規模な洪水・浸水リスクが高いです。感潮域では高潮との複合災害にも注意が必要です。 |
| 五ヶ瀬川 | 延岡市など | 上流は急峻な山間部を流れ、下流は延岡市街地を貫通します。短時間豪雨による急激な増水、氾濫が懸念されます。 |
| 小丸川 | 高鍋町、木城町など | 中・下流域に平野部が広がり、農業地帯への浸水被害のリスクがあります。急流部からの土砂流出も警戒が必要です。 |
| 耳川 | 日向市、美郷町など | 山間部から平野部へ流れ、ダム群も存在します。線状降水帯によりダムの放流が必要となる場合があり、下流への影響に注意が必要です。 |
| 一ツ瀬川 | 西都市、新富町など | 流域に広がる平野部や農地への浸水リスクがあります。河川のカーブが多い区間では、越水や堤防決壊の危険性が高まります。 |
これらの河川の増水状況は、気象庁や自治体の提供する河川水位情報、洪水警報・注意報を常に確認し、警戒水位や氾濫危険水位に達する前に、早めの避難行動をとることが命を守る上で極めて重要です。
土砂災害の危険 宮﨑県の地形と警戒すべき地域
宮﨑県は、九州山地が県土の大部分を占め、急峻な山間部が多く、地質も脆弱な箇所が点在しています。
この地形的特徴から、線状降水帯による大量の雨は、土砂災害を非常に発生させやすい環境を作り出します。
土砂災害には、土石流、がけ崩れ(崖崩れ)、地すべりなどがあり、それぞれ異なるメカニズムで発生し、甚大な被害をもたらします。
宮﨑県で警戒すべき土砂災害の種類と特徴
線状降水帯による豪雨は、地中に大量の水分を浸透させ、地盤の安定性を著しく低下させます。
これにより、これまで安全と思われていた場所でも突然土砂災害が発生する可能性があります。
| 土砂災害の種類 | 特徴と発生メカニズム | 宮﨑県における主な警戒地域 |
|---|---|---|
| 土石流 | 山腹や谷筋にたまった土砂や岩石が、集中豪雨によって一気に流れ下る現象です。破壊力が大きく、速度も速いため、避難が間に合わないことがあります。 | 九州山地を源流とする河川の谷筋、扇状地の末端、過去に土石流が発生した記録のある地域。 |
| がけ崩れ(崖崩れ) | 雨水が崖の斜面にしみ込み、地盤が緩むことで、突然斜面が崩れ落ちる現象です。住宅地や道路に隣接する急傾斜地で発生しやすく、直下にある建物に直接的な被害をもたらします。 | 急傾斜地崩壊危険箇所に指定されている地域、道路沿いの切り土・盛り土箇所、宅地造成地周辺の人工的な斜面。 |
| 地すべり | 地下水などの影響で、比較的緩やかな斜面がゆっくりと、または急速に移動する現象です。広範囲にわたって被害が及ぶことがあり、道路や家屋が破壊されることがあります。 | 地すべり防止区域に指定されている地域、粘土質の地層が分布する地域、地下水が豊富な地域。 |
宮﨑県内には、これらの土砂災害が発生しやすい「土砂災害警戒区域」や「土砂災害特別警戒区域」が指定されています。
これらの区域に居住している場合は、特に線状降水帯の発生時には、自治体からの土砂災害警戒情報や避難指示に最大限の注意を払い、迅速な避難行動をとることが重要です。
浸水被害の危険 都市部や低地の注意点
線状降水帯は、短時間に非常に大量の雨を降らせるため、河川の氾濫だけでなく、都市部や低地における浸水被害(内水氾濫)を頻繁に引き起こします。
内水氾濫とは、下水道や排水路の処理能力を超えた雨水が地表にあふれ出し、住宅地や道路、地下空間などに水がたまる現象です。
宮﨑県内の都市部や、河川沿いの低地、過去に浸水被害が発生した地域では、特に警戒が必要です。
宮﨑県内で浸水被害が発生しやすい場所と注意点
都市化が進んだ地域では、アスファルトやコンクリートで覆われた面積が広く、雨水が地面に浸透しにくいため、短時間の豪雨でも内水氾濫のリスクが高まります。
また、地形的に低い場所や、河川の堤防よりも低い「ゼロメートル地帯」に近い地域も浸水被害を受けやすいです。
| 浸水被害が発生しやすい場所 | 線状降水帯による危険性 | 具体的な注意点 |
|---|---|---|
| アンダーパス(立体交差のくぐり抜け部分) | 道路が周囲より低くなっているため、雨水が集中しやすく、急速に冠水します。水深が深くなると車が立ち往生し、脱出が困難になる危険性があります。 | 冠水している場合は絶対に進入しない。迂回経路を事前に確認しておく。 |
| 地下街、地下通路、地下駐車場 | 地上からの雨水が流れ込みやすく、一度浸水すると短時間で水位が上昇し、避難が困難になります。電気系統への影響も懸念されます。 | 大雨時は利用を避ける。避難経路や非常口の位置を把握しておく。 |
| 低地の住宅地、商店街 | 周囲より標高が低い地域は、排水が追いつかずに浸水しやすいです。特に河川に近い低地では、外水氾濫と内水氾濫の複合的な被害も考えられます。 | ハザードマップで自宅や周辺地域の浸水深を確認する。土のうや止水板などで浸水対策を講じる。 |
| マンホール周辺 | 下水道の処理能力を超えると、マンホールから雨水が逆流し、噴き出すことがあります。周囲が冠水すると、マンホールの蓋が外れて危険な場合もあります。 | 冠水時はマンホールに近づかない。足元が見えない場所は歩かない。 |
線状降水帯による豪雨時には、これらの場所を避けることが重要です。
また、自宅周辺の地形や排水状況を把握し、いざという時の避難経路や対策を事前に検討しておくことが、浸水被害から身を守るために不可欠です。

線状降水帯に備える万全の防災対策 事前準備編
線状降水帯による災害は、突発的かつ広範囲に被害をもたらす可能性があります。
しかし、事前の準備をしっかり行うことで、命の危険を回避し、被害を最小限に抑えることができます。
ここでは、宮崎県での線状降水帯発生に備えるための具体的な事前準備について解説します。
ハザードマップを確認する 危険箇所と避難経路の把握
まず、ご自身の住んでいる地域や、家族が通う学校、職場などのハザードマップを確認することが重要です。
ハザードマップは、災害が発生した場合に危険が予測される場所や、避難場所、避難経路を示した地図です。
確認すべきハザードマップの種類
宮崎県では、線状降水帯による大雨で以下のような災害が想定されます。
それぞれのハザードマップを確認しましょう。
- 洪水ハザードマップ: 河川の氾濫による浸水区域や深さ、避難場所を示します。宮崎県内の主要河川(大淀川、小丸川、五ヶ瀬川など)沿いに住んでいる方は特に重要です。
- 土砂災害ハザードマップ: 土石流、がけ崩れ、地滑りなどの危険がある区域を示します。山間部や傾斜地に隣接する地域に住んでいる方は必ず確認してください。
- 高潮ハザードマップ: 台風などによる高潮の浸水区域を示します。沿岸部に住んでいる方は確認が必要です。
- 内水氾濫ハザードマップ: 都市部の下水道や排水路の処理能力を超えた雨により、水が溢れる浸水区域を示します。都市部に住んでいる方は確認しましょう。
自宅や周辺地域の危険度を把握する
ハザードマップで、自宅や家族のいる場所がどのような危険区域に指定されているかを確認します。
また、避難経路として指定されている道路が、浸水や土砂崩れによって通行不能になる可能性がないか、代替経路も合わせて確認しておきましょう。
ハザードマップの入手方法と活用
ハザードマップは、宮崎県や各市町村のウェブサイトで公開されているほか、役所の窓口で配布されている場合もあります。
印刷して自宅に保管し、家族全員で危険箇所や避難経路を共有し、日頃から意識しておくことが大切です。
避難場所と避難経路の確認 宮﨑県内の指定避難所情報
ハザードマップで危険箇所を確認したら、実際にどこへ避難するのか、どのような経路で避難するのかを具体的に決めておきましょう。
指定避難所の種類と確認ポイント
避難所には、主に「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の2種類があります。
- 指定緊急避難場所: 災害が発生または発生するおそれがある場合に、緊急的に避難し、身の安全を確保する場所です。一時的な避難に適しています。
- 指定避難所: 災害の危険性がなくなり、自宅へ戻るまでの間、一定期間滞在する場所です。食料や物資の供給、生活支援が行われます。
安全な避難経路の確認とシミュレーション
避難経路は、一つだけでなく、複数確認しておくことが重要です。
線状降水帯による豪雨では、道路の冠水や土砂崩れなどで、通常の避難経路が使えなくなる可能性があります。
夜間や悪天候時でも安全に移動できるか、実際に家族で歩いてみるなどしてシミュレーションしておくと良いでしょう。
非常持ち出し袋の準備と備蓄品の確認
災害発生時にすぐに持ち出せる「非常持ち出し袋」と、自宅で避難生活を送るための「備蓄品」の準備は、命と生活を守る上で非常に重要です。
非常持ち出し袋(一次持ち出し品)の準備
避難時にすぐに持ち出す、必要最低限のものをまとめたものです。
両手が空くリュックサックなどに、以下のものを入れておきましょう。
定期的に中身を確認し、使用期限のあるものは入れ替えてください。
| カテゴリ | 具体的な品目 | ポイント |
|---|---|---|
| 食料・飲料 | 飲料水(500mlペットボトル数本) | 一人1日3リットルを目安に |
| 非常食(乾パン、栄養補助食品など) | 調理不要で日持ちするもの | |
| アメ、チョコレートなど | 糖分補給、気分転換に | |
| 貴重品・情報 | 現金(小銭含む) | 公衆電話や自動販売機用 |
| 健康保険証、免許証のコピー | 身分証明、手続きに必要 | |
| 家族の写真、連絡先メモ | 安否確認に役立つ | |
| 衛生用品・医薬品 | 常備薬、お薬手帳 | 持病がある方は必須 |
| 絆創膏、消毒液など救急用品 | 怪我の応急処置に | |
| ウェットティッシュ、携帯トイレ | 水が使えない場合に備える | |
| 生理用品、おむつ、粉ミルク | 乳幼児や女性がいる場合 | |
| その他 | 懐中電灯、予備電池 | 夜間や停電時に必要 |
| 携帯ラジオ、予備電池 | 情報収集に不可欠 | |
| 軍手、ビニール袋 | 作業やゴミ処理に | |
| 防寒具、雨具 | 体温調節や雨対策 |
備蓄品(二次持ち出し品・自宅避難用)の確認
自宅で数日間生活するための備蓄品です。
ライフラインが停止しても、最低3日分、できれば7日分以上の水や食料、生活用品を備蓄しておきましょう。
「ローリングストック法」を取り入れ、普段使いの食品を多めに買い置きし、使った分だけ買い足すことで、常に新しい備蓄品を保つことができます。
- 飲料水: 一人1日3リットルを目安に、最低3日分(9リットル)以上。
- 非常食: カセットコンロとガスボンベ、レトルト食品、缶詰、フリーズドライ食品など、調理しやすいもの。
- 簡易トイレ: 断水時に備え、凝固剤付きのものを複数。
- 生活用品: トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ライター、ラップ、アルミホイル、カセットコンロ、ガスボンベなど。
- 情報収集: スマートフォン用モバイルバッテリー、充電器。
定期的な点検と見直し
非常持ち出し袋も備蓄品も、準備したら終わりではありません。
定期的に中身を確認し、食料や水の賞味期限、電池の残量などをチェックしましょう。
家族構成の変化(乳幼児の誕生、高齢者の介護など)に合わせて、必要なものを追加・見直すことも大切です。
家族との連絡手段と安否確認方法の共有
災害時に家族が離れ離れになった場合、互いの安否を確認し、連絡を取り合う手段を事前に決めておくことが重要です。
電話回線が混み合う可能性を考慮し、複数の方法を共有しておきましょう。
災害用伝言サービスを活用する
- 災害用伝言ダイヤル(171): 音声で安否情報を録音・再生できるサービスです。電話番号をキーに伝言をやり取りします。
- 災害用伝言板(web171): インターネットを通じて文字で安否情報を登録・確認できるサービスです。
- 携帯電話会社の災害伝言サービス: 各携帯電話会社が提供するサービスで、安否情報を登録・閲覧できます。
安否確認方法と集合場所の共有
災害時に自宅に戻れない場合を想定し、家族が集合する場所を複数決めておきましょう。
例えば、親戚の家、公共施設、特定の公園などです。
また、離れて暮らす親戚や友人と、連絡が取れなくなった場合の安否確認方法(例:特定のSNSグループで連絡、共通の知人を介して確認など)を決めておくことも有効です。
災害時はSNSが有効な情報源となる一方で、誤情報も拡散されやすい特性があります。
家族間で「このアカウントの情報は信頼できる」というものを共有しておくのも良いでしょう。
防災情報の入手方法と活用 気象庁や自治体の情報源
線状降水帯発生の可能性が高まった際や、実際に発生した際には、最新の防災情報を迅速に入手し、適切な行動をとることが命を守る上で不可欠です。
信頼できる情報源を事前に把握しておきましょう。
気象庁からの情報
- 気象庁ウェブサイト: 線状降水帯に関する情報(発生予測、解析情報など)、大雨特別警報、洪水警報・注意報、土砂災害警戒情報など、様々な防災情報が発表されます。特に「キキクル(危険度分布)」は、土砂災害、浸水害、洪水の危険度を色分けで示しており、視覚的に状況を把握するのに役立ちます。
- 線状降水帯予測情報: 気象庁は、線状降水帯が発生する可能性のある半日程度前から、その予測情報を発表します。この情報が出たら、特に警戒を強めましょう。
宮崎県および市町村からの情報
- 宮崎県防災情報ポータルサイト: 県内の避難情報、気象情報、河川水位情報などが集約されています。
- 各市町村のウェブサイト: 各自治体が発令する避難情報(高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保など)や、開設される避難所の情報が掲載されます。
- 防災メール、防災アプリ、SNS: 各自治体が提供する防災メールサービスや、公式SNSアカウント(Twitter、Facebookなど)を登録・フォローすることで、プッシュ通知で情報を得ることができます。
テレビ・ラジオ・携帯電話の緊急速報
- テレビ(NHK、民放各局): 災害時には特別番組が組まれ、詳細な気象情報や避難情報が提供されます。テレビのリモコンでデータ放送を活用すると、地域ごとの詳細情報も確認できます。
- ラジオ: 停電時でも情報を得られる重要な手段です。電池式のラジオを準備しておきましょう。
- エリアメール・緊急速報メール: 携帯電話会社から、災害時に緊急性の高い情報(避難情報など)が自動的に配信されます。設定を確認しておきましょう。
防災アプリの活用
気象情報、避難情報、ハザードマップなどを一元的に確認できる防災アプリも多数提供されています。
いくつかダウンロードしておき、使い慣れておくことをお勧めします。
これらの情報源を複数活用し、常に最新の状況を把握することで、線状降水帯による危険から身を守るための適切な判断と行動につながります。

線状降水帯発生中の命を守る行動 危険を回避する対策
線状降水帯が発生し、宮﨑県に甚大な被害をもたらす可能性が高まった場合、命を守るための迅速かつ適切な行動が求められます。
ここでは、線状降水帯が活発化している最中に取るべき具体的な対策について解説します。
最新の気象情報を常に確認する
線状降水帯は、同じ場所に長時間停滞し、局地的に猛烈な雨を降らせる特性があります。
そのため、刻一刻と変化する気象情報をリアルタイムで把握することが、身の安全を守る上で最も重要です。
- 気象庁の発表を注視する: 気象庁が発表する気象情報、警報・注意報、線状降水帯発生情報、土砂災害警戒情報、洪水警報等を常に確認してください。特に「顕著な大雨に関する情報」が発表された場合は、命の危険が迫っていることを意味します。
- 宮﨑県および市町村の防災情報を確認する: 各自治体から発令される避難情報(高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保など)や、河川水位、土砂災害の危険度に関する情報に注意を払いましょう。
- 複数の情報源を活用する: テレビ、ラジオ、インターネット(気象庁ウェブサイト、宮﨑県・各市町村の防災ウェブサイト)、防災アプリ、防災無線、緊急速報メールなど、様々な手段で情報を入手し、情報の信頼性を確認しましょう。スマートフォンは充電を十分に行い、いつでも情報が得られる状態にしておくことが大切です。
避難情報のレベルと適切な行動
宮﨑県内で線状降水帯が発生した場合、自治体は住民の命を守るために「警戒レベル」に応じた避難情報を発令します。
これらのレベルを正しく理解し、適切な行動を速やかに取ることが、命を守る上で不可欠です。
以下の表で、警戒レベルごとの取るべき行動を再確認し、自身の状況と照らし合わせて行動しましょう。
| 警戒レベル | 名称 | 住民がとるべき行動 | 宮﨑県での注意点 |
|---|---|---|---|
| 警戒レベル1 | 早期注意情報 | 災害への心構えを高める | 気象情報に注意し、ハザードマップで自宅周辺の危険箇所を確認 |
| 警戒レベル2 | 大雨注意報・洪水注意報など | ハザードマップで避難経路を確認、非常持ち出し袋の準備 | 避難経路の安全性を再確認し、避難準備を整える |
| 警戒レベル3 | 高齢者等避難 | 危険な場所から高齢者や障害のある方、乳幼児など避難に時間のかかる人が避難を開始する | 対象者は速やかに安全な場所へ避難。その他の住民も避難準備を完了 |
| 警戒レベル4 | 避難指示 | 危険な場所から全員避難 | 対象地域の住民は全員、速やかに指定避難所や安全な親戚・知人宅へ避難。 |
| 警戒レベル5 | 緊急安全確保 | 命の危険が迫っており、直ちに安全な場所へ移動 | 既に災害が発生、または切迫している状況。命を守る最善の行動(自宅の安全な場所への移動など)を取る。 |
避難のタイミングを逃さない
避難指示が発令されてからでは、すでに避難経路が危険になっている可能性があります。
警戒レベル3(高齢者等避難)の段階で、避難に時間のかかる家族がいる場合は、早めに避難を開始することが重要です。
また、夜間の避難は危険が伴うため、明るいうちの避難を心がけましょう。
安全な場所への速やかな避難
避難情報が発令されたら、ためらわずに安全な場所へ移動することが命を守る上で最も重要です。
事前に確認した避難場所や避難経路に従い、冷静に行動しましょう。
避難時の注意点と持ち物
- 服装と履物: 動きやすく、濡れてもよい服装を選び、長靴やスニーカーなど滑りにくく、足元を保護できる履物を着用しましょう。
- 非常持ち出し袋の携行: 事前に準備した非常持ち出し袋を必ず持って避難してください。貴重品、水、食料、常備薬、携帯ラジオ、懐中電灯、モバイルバッテリーなどが含まれているか再確認しましょう。
- 高齢者や子供、ペットへの配慮: 避難に時間がかかる場合は、早めに避難を開始し、周囲の助けも借りましょう。ペットを飼っている場合は、同行避難が可能な避難所か確認し、必要な準備を整えてください。
- 安全な経路の選択: 冠水している道路や、崖や急斜面の近く、増水した河川沿いの道は避け、より安全な経路を選びましょう。
自宅に留まる場合の安全確保
避難場所への移動が危険な場合や、自宅がハザードマップ上の危険区域外である場合は、自宅内で安全を確保する「垂直避難」も有効な手段です。
- 自宅の安全な場所への移動: 浸水のおそれがある場合は、建物の2階以上の、より高い場所へ移動しましょう。土砂災害のおそれがある場合は、崖や斜面から離れた部屋へ移動し、窓から離れてください。
- 屋根の上への避難は最終手段: 孤立し、他に安全な場所がない場合の最終手段として考えられますが、非常に危険を伴います。救助を待つ間、体力消耗を防ぎ、安全を確保できる場所に留まりましょう。
屋外での危険を避ける行動
線状降水帯発生中は、屋外には多くの危険が潜んでいます。
不要不急の外出は控え、やむを得ず屋外にいる場合は、以下の点に注意し、危険を回避する行動をとりましょう。
- 増水した河川や用水路に近づかない: 急な増水や氾濫のおそれがあります。見た目よりも流れが速く、深さも不明なため、絶対に近づかないでください。宮﨑県内の主要河川(大淀川、五ヶ瀬川など)の周辺は特に注意が必要です。
- 冠水した道路を通行しない: 車での通行は、水深が不明なため非常に危険です。エンジンが停止するだけでなく、流される危険もあります。歩いての通行も、足元が見えず、側溝やマンホールに転落するおそれがあります。
- アンダーパスの危険性: 道路が立体交差しているアンダーパスは、短時間で冠水し、非常に危険です。水深が浅く見えても、急激に水位が上昇することがあるため、絶対に進入しないでください。
- 土砂災害の兆候に注意: 崖や急斜面から異音がする、ひび割れが見られる、小石が落ちてくるなどの兆候があった場合は、直ちにその場から離れてください。宮﨑県は山間部が多いため、特に注意が必要です。
- 落雷や突風に警戒: 線状降水帯に伴い、落雷や突風が発生することもあります。頑丈な建物の中に避難し、屋外にいる場合は、電柱や木の下など危険な場所を避けましょう。
車での移動中の注意点
運転中に線状降水帯による大雨に遭遇した場合は、無理に走行を続けず、安全な場所に停車するか、引き返すことを検討しましょう。
視界不良や路面状況の悪化は、交通事故のリスクを高めます。
徒歩での移動中の注意点
やむを得ず徒歩で移動する場合は、足元に十分注意し、側溝やマンホール、増水した水路などが見えなくなっている可能性があるため、慎重に行動してください。
懐中電灯などで足元を照らしながら移動すると安全性が高まります。

線状降水帯通過後の行動と復旧支援
線状降水帯が通過し、直接的な危険が去った後も、安心はできません。
二次災害のリスクや生活再建に向けた課題が多く残されています。
ここでは、宮﨑県内で線状降水帯による被害が発生した後、安全を確保し、速やかに生活を立て直すための行動と、利用できる支援情報について解説します。
安全確認と二次災害への注意
線状降水帯による豪雨が止んだ後も、地盤の緩みや建物の損傷など、見えない危険が潜んでいます。
自宅や周辺の安全を慎重に確認し、新たな被害を招かないよう注意深く行動することが重要です。
自宅の安全確認
自宅に戻る際は、まず建物の外観に異常がないか確認し、安全が確認できてから中に入りましょう。
浸水被害があった場合は、電気のブレーカーを落とし、ガスの元栓を閉めてから作業を開始してください。
通電火災や漏電の危険性があるため、専門家による点検を受けるまで安易に電気を使用しないようにしましょう。
屋根や壁、基礎部分のひび割れ、傾きなども注意深く確認してください。
周辺環境と二次災害への警戒
河川の水位が下がっていても、堤防や護岸が弱くなっている可能性があります。
また、土砂災害警戒区域や急傾斜地周辺では、雨が止んだ後も土砂崩れが発生する危険性が高まります。
むやみに危険な場所へ近づかないでください。
冠水した道路には側溝やマンホールが開いている可能性があり、見えない危険が潜んでいます。
水が引いた後も、地盤が緩んでいるため、車両の通行や徒歩での移動には十分な注意が必要です。
衛生管理と感染症対策
浸水した家屋や物品には、泥や汚水とともに細菌やウイルスが付着している可能性があります。
清掃作業を行う際は、ゴム手袋やマスクを着用し、適切な消毒を行いましょう。
手洗いやうがいを徹底し、感染症の予防に努めてください。
特に、破傷風やレプトスピラ症など、泥水から感染する病気にも注意が必要です。
被災後の生活再建に向けた情報収集
被災後の生活再建には、様々な手続きや支援が必要となります。
正確な情報をいち早く入手し、適切な支援に繋げることが重要です。
情報収集の主な手段と、必要となる可能性のある手続きについて確認しましょう。
情報収集の手段
被災後の生活再建に関する情報は、主に以下の情報源から得ることができます。
- 市町村役場の窓口やウェブサイト
- 宮﨑県庁の防災関連部署のウェブサイトや広報
- テレビ、ラジオ、インターネットニュース
- SNS(自治体公式アカウントなど)
- 地域住民の集まりや避難所での情報共有
特に、お住まいの市町村からの情報が最も重要です。
広報誌やウェブサイト、防災行政無線などに注意を払いましょう。
罹災証明書の発行申請
被災した建物や家財の損害状況を証明する「罹災証明書」は、公的な支援を受ける上で非常に重要です。
市町村の窓口で申請し、被害状況の調査を受ける必要があります。
保険金の請求や税の減免、各種支援制度の利用に必要となるため、速やかに手続きを行いましょう。
主な生活再建支援制度
被災後の生活再建を支援するための制度には、以下のようなものがあります。
具体的な内容は、被害の程度や自治体によって異なりますが、一般的に利用される可能性のある制度です。
| 支援の種類 | 内容の概要 | 主な利用目的 |
|---|---|---|
| 災害救助法に基づく支援 | 応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理、被災者生活再建支援金など | 住居の確保、住宅の修繕、生活の立て直し |
| 被災者生活再建支援制度 | 住宅の被害程度に応じて支給される支援金(国と地方自治体) | 住宅の再建・補修、生活基盤の再構築 |
| 災害援護資金貸付制度 | 被災世帯に対する低利または無利子の貸付 | 生活用品の購入、医療費、学費など一時的な出費 |
| 義援金・見舞金 | 国や地方自治体、日本赤十字社などから支給される金銭 | 被災者への見舞い、生活の足し |
| 税の減免・猶予 | 所得税、住民税、固定資産税などの減免や納税猶予 | 税負担の軽減 |
これらの制度の詳細は、お住まいの市町村の窓口や、宮﨑県の担当部署に問い合わせることで確認できます。
必要に応じて専門家(弁護士、司法書士など)や相談窓口を利用することも検討しましょう。
宮﨑県からの支援情報
宮﨑県は、国や市町村と連携し、被災された方々の生活再建を多角的に支援するための情報を提供しています。
県独自の支援策や、県が窓口となる情報もありますので、積極的に活用しましょう。
宮﨑県庁の災害対策情報
宮﨑県庁の公式ウェブサイトでは、災害発生時に被災者支援に関する最新情報が随時更新されます。
支援制度の案内、相談窓口の一覧、義援金の受付状況、ボランティア情報の募集などが掲載されますので、定期的に確認しましょう。
心のケアと健康支援
被災後は、精神的なストレスや疲労が蓄積しやすくなります。
宮﨑県では、被災者の心のケアを目的とした専門相談窓口や、保健師による健康相談の機会を提供しています。
不安や不調を感じたら、我慢せずに相談しましょう。
災害ボランティアの活用
宮﨑県社会福祉協議会などが中心となり、災害ボランティアセンターが設置されることがあります。
家屋の片付けや泥出しなど、人手が必要な場合は、ボランティアの支援を受けることができます。
また、自身が支援できる場合は、ボランティアとして活動に参加することも、復旧への大きな力となります。
線状降水帯による災害は、私たちの生活に甚大な影響を及ぼす可能性があります。
しかし、適切な事後対応と、利用できる支援を最大限に活用することで、一歩ずつ生活再建を進めることができます。
常に最新の情報を入手し、一人で抱え込まず、周囲や公的機関のサポートを積極的に求めましょう。

まとめ
宮﨑県は線状降水帯による洪水や土砂災害、浸水のリスクが高い地域です。
大切な命を守るためには、ハザードマップでの危険箇所の確認、避難場所と経路の把握、非常持ち出し袋の準備といった事前の備えが何よりも重要です。
また、線状降水帯発生時には、最新の気象情報を常に確認し、自治体からの避難情報に沿って速やかに安全な場所へ避難する行動が求められます。
日頃からの防災意識を高め、適切な対策を講じることで、災害から身を守り、安心して生活できる宮﨑県を目指しましょう。