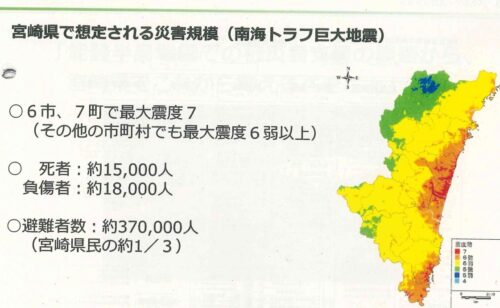家の形状で耐震性能が変わる!凹凸の少ない四角い家が地震に強い理由とは
2025年04月15日

耐震性に優れた家を建てるには、基礎や構造材だけでなく「家の形状」が極めて重要です。実は、凹凸の少ない四角い家は、複雑な形状の家に比べて地震エネルギーをバランスよく分散でき、倒壊リスクを大幅に軽減できます。この記事では、四角い家が地震に強い理由から、具体的な耐震構造、過去の震災事例に基づいた倒壊傾向、設計時や補強時のポイントまで、建築・防災の視点も交えて徹底解説します。
目次
家の形状と耐震性能の関係とは
建物形状が地震の揺れに与える影響
地震が発生した際、建物に加わる揺れは建物の構造的な形状によって増幅されたり減衰されたりする特徴があります。とりわけ平面形状や立体構造が不均衡であったり、凹凸が多かったりする住宅は、地震エネルギーの伝わり方に偏りが出るため、特定箇所に負荷が集中しやすくなります。これが応力集中の原因となり、耐震性能を低下させる要因となります。
一方で、シンプルな形状の建物は、揺れを均等に受け止めやすいため、全体としての構造が健全に保たれやすいのです。特に日本は地震の多い国であり、住宅の設計段階においては、建物形状の安定性が非常に重要視されています。
四角い家と複雑な形状の家の構造的な違い
建物の平面形状にはさまざまなタイプがありますが、よく比較されるのは「総二階の四角い家」と「L字型やコの字型、張り出しや吹き抜けのある複雑な形状の家」です。以下の表に、四角形と複雑形状の構造的な違いを整理しました。
| 形状の種類 | 耐震性の特性 | 構造的な課題 |
|---|---|---|
| シンプルな四角い家(総二階) | 剛性・重心のバランスが良好で、地震力を均等に分散 | 構造計算通りに力が流れるため、設計通りの耐震性を確保しやすい |
| L字型・コの字型の家 | 平面的な不整形により振動応答が複雑化 | 形状によっては応力が集中しやすく、接合部や隅部から損傷が始まりやすい傾向がある |
| 吹き抜け・片持ち梁を含む家 | 強度の不均衡により階ごとの揺れが異なる | 壁量が不足する部分が生まれ、構造補強が必要となるケースが多い |
一般に、「直方体」や「正方形」など安定した形状は、構造的にバランスが良いとされ、耐震設計上でも有利です。これに対して、張り出し部分、変形構造、吹き抜け、高天井などは設計上の工夫を要し、多くの場合追加の構造補強が必要となります。
また、建築基準法では建物の耐震設計に関して最低限の基準を定めていますが、建築物の形状や構造計画に正確な配慮をしなければ、法律を満たしていても被害が大きくなるおそれがあります。たとえば、大地震時には「1階のガレージ部分が潰れた」といったケースがあるように、形状による弱点が顕著に現れるのです。
このように、住宅の形状は耐震性能に直結する重要な要素です。ただし、複雑な形状の住宅がすべて危険というわけではなく、適切な設計と補強によって安全性を高めることは可能です。その土台として、安定した構造計画と合理的な形状選定が求められるのです。

凹凸の少ない四角い家が地震に強い理由
構造力学から見る四角形の安定性
四角い家は基本的に形状が均一で、構造的にバランスが取りやすいという特性を持っています。建築において、地震のエネルギーを受け流すためには、力の伝達経路に無理がなく、一体的に揺れに耐える構造が求められます。方形に近い住宅形状は、力学的に剛性を均等に保ちやすく、変形の少ない構造とすることが可能です。
特に、建物の外形が矩形(長方形や正方形)に近いと、地震力が均等に伝達されやすくなります。構造体が連続的かつ一貫していることで、局所的な応力集中を避けられ、全体として耐震性能が高く保たれます。
耐力壁と剛性のバランスの良さ
耐震性を確保するためには、耐力壁の配置バランスが非常に重要です。四角い家では壁の配置が均等になりやすく、建物全体の剛性バランスが取りやすいというメリットがあります。これにより、ある一方向だけが過度に剛性を持ち、それが原因でねじれ(トルク)が発生してしまう事態を避けることができます。
以下は、耐震設計上重要な要素と四角い家との相性を示した表です。
| 耐震設計要素 | 四角い家の特性 | 耐震性への影響 |
|---|---|---|
| 耐力壁の配置 | 左右対称にしやすい | 建物のねじれを防げる |
| 剛性の均等分布 | 無駄な変形が起きにくい | 地震力を均一に吸収可能 |
| 接合部の簡素化 | 複雑な接合部が不要 | 施工精度と耐久性が向上 |
このように四角形の住宅は、設計段階から力学的に安定した耐震構造を実現しやすいという利点があります。
力の分散と重心の安定性
地震動が建物に加わった際には、揺れの力(地震力)が建物内をどのように伝わり、どこに集中するかが耐震性の要となります。四角い家は、構造が均一であるため、重心と剛心のズレが起きにくく、それによって生じるねじれモーメントを抑えることができます。
また、地震力は建物の重心に近い部分で支えられるため、重心が建物の中央に近いほど、支点との距離が短くなるなど力の分散が最適化されます。四角い家は左右対称や上下対称といった対称性が設計に反映されやすく、それにより重心と剛心が近づく傾向にあります。
一方、L字型やコの字型などの凹凸の多い形では、どうしても重量バランスが偏り、一部に力が集中してしまいやすくなります。その結果、特定の柱や耐力壁に過剰な応力がかかり、部分破壊や倒壊リスクが高まることになります。

凹凸が多い家はなぜ揺れに弱いのか
形状不整による応力集中のリスク
建物に凹凸が多い、すなわちL字型やコの字型などの複雑な平面形状を持つ住宅は、地震時に「形状不整」の状態となります。形状不整とは、建物の平面配置や立面が均質でなく、構造バランスに偏りがあることを指します。このような形状では、揺れによって建物各部にかかる力(応力)が一様に分散されず、特定の部分に集中しやすくなるため、耐震性能が著しく低下します。
特に建物の角部分や突き出した部分、くびれている部分などには、強い応力が生じ、ひび割れや構造部材の破損が発生しやすいとされています。これは「応力集中」と呼ばれる現象で、構造力学の観点からも建物が破壊しやすくなる原因とされています。
増改築で生まれる構造の不均一化
凹凸の多い住宅の中には、元々は単純な形状であった建物が後からの増築や減築を繰り返すことで、複雑な形状となっているケースも多く見受けられます。しかしこのような増改築は、多くの場合、構造的な観点から一貫した設計がなされていないため、壁量や耐力壁の配置バランスが悪くなり、耐震性が著しく低下します。
また、増築部分に柱や梁の配置が不足していたり、土台の接合が不十分である場合、地震時に脱落や倒壊のリスクを伴う重大な構造的不具合につながります。特に築年数が古い住宅では、旧耐震基準のままであることが多いため、増改築による構造の不均一化は、さらに深刻な耐震性の低下要因となります。
耐震補強の難易度と施工コスト
凹凸の多い家は、耐震補強工事の際にも大きな課題となります。なぜなら壁の配置が不均等であることで、耐震補強の対象面積が広がるうえに、補強の方法も複雑化するからです。平面が単純な四角形の住宅であれば、耐力壁の設置や金物補強を規則的かつ効率よく行うことができますが、凹凸の多い住宅では補強箇所の特定や構造解析の難易度が高く、設計・施工ともに高いレベルの技術と費用が求められます。
以下の表に、住宅形状の違いによる耐震補強の難易度とコストの違いを示します。
| 住宅形状 | 構造設計の難易度 | 耐震補強コスト | 施工のしやすさ |
|---|---|---|---|
| 単純な四角形 | 低 | 低〜中 | 高 |
| L字型 | 中 | 中〜高 | 中 |
| コの字型・複雑形状 | 高 | 高 | 低 |
このように、凹凸の多い住宅は耐震補強が技術的にも金銭的にも難しい建築形態となり、それゆえに多くの住宅が十分な耐震対策を施されないまま放置されている現実があります。
また、施工者によっては構造計算を行わずに安易に補強を行ってしまうケースもあり、かえって建物の構造バランスを崩してしまう恐れもあります。凹凸の多い家では、必ず構造設計に精通した専門の建築士による詳細な耐震診断と補強設計が必要です。

実際の地震被害から見る家の形状と耐震性
阪神淡路大震災や東日本大震災の被害事例
日本ではこれまでに数多くの地震が発生しており、そのたびに住宅の耐震性能に関する課題が浮き彫りになってきました。中でも1995年の阪神淡路大震災と2011年の東日本大震災は、住宅被害の規模と内容から多くの教訓をもたらしました。
阪神淡路大震災では、旧耐震基準で建てられた木造住宅を中心に多くの建物が倒壊。この地震で特に被害が目立ったのは、「L字型」や「コの字型」など凹凸の多い複雑な平面形状の住宅でした。これらの多くは、構造計算がされていない在来工法で、耐力壁の配置バランスが悪かったために、ねじれや局所的な応力集中により倒壊したのです。
東日本大震災でも、沿岸部を中心に津波の被害による破壊が顕著でしたが、内陸部の揺れによる倒壊もいくつか見られました。このときも矩形に近い整った形状を持つ建物は倒壊を免れたケースが多く、建物形状の重要性が再認識されました。
住宅形状ごとの倒壊率の違い
実際の被害状況から得られた統計データにも、住宅形状と耐震性の相関が見てとれます。以下の表は、阪神淡路大震災での住宅の平面形状別倒壊率を示したものです。
| 住宅の平面形状 | 倒壊率(震度7地域) |
|---|---|
| 正方形・長方形(凹凸なし) | 約15% |
| L字型 | 約34% |
| コの字型 | 約42% |
| 折れ線型(段差のある形) | 約37% |
このように、凹凸の少ない整形の住宅ほど倒壊率が低いことが明らかになっています。形状によって耐力壁の配置や力の分散に差が生まれることが、被害の程度に影響していると考えられています。
専門家による形状と被害の分析
建築学、特に構造工学の専門家たちも、従来の震災調査をもとに住宅形状と耐震性能の関係性を分析しています。東京大学地震研究所や建築研究所の報告では、住宅の形状が「シンプルで対称」であることが、揺れに対して最も有効な対策のひとつであるとされています。
例えば、建物が非対称なL字型やT字型の場合、地震動による揺れの際に「ねじれ」が発生しやすく、構造的な弱点が露呈しやすくなります。この「ねじれ」は、設計段階での重心と剛心のズレによって生じるもので、耐震設計における重大な検討事項です。
さらに、民間の建築士団体などによる調査でも、増改築や出っ張り・引っ込みの多い間取りが地震時の弱点になることが指摘されており、このような住宅に対しては耐震リフォームを積極的に行うべきであるとしています。
このような専門家の見解は、建築基準法改正や住宅性能表示制度の改善にも反映されており、耐震性能を確保するうえで建物形状が非常に重要な要素であることを行政も認めている証といえます。

四角い家に向いている耐震構造の工法とは
耐震等級と構造計算の基礎知識
住宅の耐震性能を評価する上で重要なのが「耐震等級」です。これは建築基準法レベルの耐震性を基準に、等級1(最低基準)〜等級3(最高基準)までの3段階で評価されます。特に地震に強い家を目指すなら、耐震等級3の取得が理想です。これは消防署や警察など、防災の拠点となる建物と同レベルの耐震性です。
また、耐震等級を取得するには、構造計算(構造設計)が必要であり、建物の形状や間取り、使用する材料、地盤条件などを精密に検討した上で設計が行われます。特に凹凸の少ない四角い家は、構造計算の精度が上がりやすく、耐震性能を確保しやすい形状とされています。
在来工法・ツーバイフォー工法・鉄骨造の比較
住宅の耐震性能は、採用する工法によっても左右されます。ここでは、四角い形状の住宅に適した代表的な構造工法である、在来工法(木造軸組工法)・ツーバイフォー(2×4)工法・鉄骨造の特徴を比較します。
| 工法 | 特徴 | 四角い家との相性 | 耐震性 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 在来工法 (木造軸組み工法) |
柱と梁で骨組みを作る伝統的な方法。間取りの自由度が高い。 | 正方形・長方形の建物と相性が良く、力の流れが整理しやすい。 | 筋交いや耐力壁の配置によって高められる。 | 設計・施工の質により性能差が大きい。耐震等級3に対応するには構造計算が必須。 |
| ツーバイフォー工法 (枠組壁工法) |
壁で建物を支える構造。面で力を受けるため地震に強い。 | 角形の家に適しており、壁量計算に基づく合理的な構造が組みやすい。 | 高い。等級3も十分可能。 | 開口部(窓やドア)の多い設計には不向き。 |
| 鉄骨造 | 鋼材を用いた構造で広い空間や変形に強い。 | シンプルな形状であれば設計の自由度と耐震性のバランスが良い。 | 高い耐震性が得やすく、構造計算も明瞭。 | コストが木造より高くなりがち。専門設計が必須。 |
このように、四角い家は形状の安定性から、どの工法を選んでも高い耐震性能を引き出しやすく、設計と施工がしやすいという特長があります。そのうえで、ライフスタイルや予算、土地の条件に応じた工法の選定が重要です。
地震に強い設計のポイント
工法とともに検討すべきなのが具体的な設計上の工夫です。以下のようなポイントを押さえることで、四角い家の持つポテンシャルを最大限に活かすことができます。
- 耐力壁のバランス配置:建物の四隅や壁面に配置し、地震力を均等に受ける設計にする。
- 開口部(窓・ドア)配置の工夫:南側を中心に大きな開口をとる場合でも、耐力壁とのバランスを考慮する。
- 断面の単純化:L字型やコの字型よりも、凹凸のない単純な四角形の方が応力の集中を防ぎやすい。
- 剛心と重心の一致:ねじれを防止するため、構造的な中心と建物の重心を近づける。
これらの工夫はいずれの工法を採用する場合でも有効ですが、特にツーバイフォー工法や鉄骨造では設計通りに剛性を確保しやすく、有利に働くことが多いです。
また、これらの設計が効果を発揮するには、信頼できる建築士や構造設計士との連携が不可欠です。耐震性能の高い住宅づくりには、見た目だけでなく構造のバランス・整合性を意識した設計が求められます。

新築時に注意したい地震に強い設計のポイント
重心と剛心を一致させる平面計画
住宅の耐震設計を行う際、建物の「重心」と「剛心」をできるだけ一致させることが非常に重要です。重心とは建物全体の重さの中心であり、剛心とは建物の剛性(硬さ)の中心です。この2つが大きくずれていると、地震の揺れによって建物がねじれる「ねじれ変形」が生じやすくなり、特に柱や壁に局所的な負担が集中してしまいます。
例えばL字型住宅やコの字型住宅などの形状不整な建物は、重心と剛心のズレが起こりやすい傾向にあります。設計段階で平面プランを見直し、左右対称かつ長方形や正方形になるよう工夫することで、力が分散しやすい安定した構造が実現できます。
間取りと開口部のバランス
新築住宅ではデザイン性を重視するあまり、大きな窓や吹き抜け、開放的なリビングを設計することがあります。しかし開口部(窓やドア)が多すぎると、耐力壁が不足し住宅全体の耐震性能が低下するリスクがあります。
とくに南側に掃き出し窓を連続して配置した場合、耐力壁が少なくなり構造的不均等が生じます。間取り設計では、開口部の数や大きさ、配置を検討しながら、各方向にバランスよく耐力壁を配置することが求められます。
また、吹き抜け部分についても、2階部分の構造(梁や床組)に大きく影響するため、耐震設計上の配慮が必要です。意匠性と構造のバランスを考慮することが、地震に強い住まいづくりにつながります。
地盤との相性も重要
いかに建物の形状や構造が優れていても、建てる場所の地盤が弱ければ期待する耐震性能は得られません。新築計画の際は必ず地盤の調査を行い、地盤に適した基礎構造と建物形状を選択する必要があります。
以下に、主な地盤種別とそれに適した基礎の種類を表にまとめます。
| 地盤の種類 | 特徴 | 適した基礎構造 |
|---|---|---|
| 良好な地盤(支持力十分な砂礫層など) | 不同沈下のリスクが低く、揺れも抑えやすい | ベタ基礎、布基礎 |
| 軟弱地盤(粘土質・埋立地など) | 液状化や沈下のリスクがある | 表層改良+ベタ基礎、杭基礎 |
| 造成地・崖地 | 地滑り・土砂崩れの危険がある | 地盤補強+深基礎 or 杭基礎 |
地盤と建物の相性が悪いと、余計な応力がかかり、地震の揺れで建物が傾く・沈下する可能性があります。地盤調査には「スウェーデン式サウンディング試験(SWS試験)」などが用いられ、専門の地盤調査会社や住宅会社に依頼するのが一般的です。
さらに、地盤調査結果をもとに構造計算を行うことで、より地震に強い設計が可能になります。造成地などリスクの高い場所に建築する場合は、専門家による構造解析や第三者機関の検査を併用することが望ましいです。

既存住宅を補強する際の形状リスク対策
凹凸を解消するリフォーム方法
既存住宅において、建物形状に凹凸が多い場合は耐震性能が低下しやすく、応力集中や剛性のバランスが崩れるといった地震時の倒壊リスクを高める要因になります。これを踏まえ、住宅の形状的な弱点を補うリフォームは、地震に強い構造へと改善するために非常に重要です。
建物外形の凹部分を減らすためには、隅切りや増築によって「矩形(くけい:長方形・正方形)」に近づける設計が有効です。これにより、強度分布の均一化と建物のねじれを防止する効果が期待されます。
また、バルコニーや張り出し部分を撤去・補強して形を整えることも可能です。リフォーム時は耐力壁や接合部の新設・増設も行い、建物全体の剛性バランスを整えることで、安全性を向上させることができます。
耐震診断の活用と補助制度
既存建物の耐震性能を正確に把握するために、耐震診断の実施は不可欠です。1981年以前に建てられた建物(旧耐震基準に基づく)は、特に倒壊リスクが高いため、早急な診断が推奨されます。
耐震診断では、以下のような項目を詳細に評価します。
| 診断項目 | 内容 |
|---|---|
| 建物の形状 | 平面・立面の凹凸の程度、左右対称性、建物配置のバランス |
| 耐力壁の配置 | バランスの良い間取りか、壁量が不足していないか |
| 基礎の健全性 | クラック、不同沈下、鉄筋の有無など |
| 接合部の状況 | 金物による固定の有無、隅角部の補強の適切性 |
また、国や自治体では耐震診断および耐震改修に対する補助制度が設けられており、条件を満たせば数十万円の補助を受けられるケースもあります。対象や条件、申請方法は自治体によって異なるため、各市区町村の住宅課などに確認することが大切です。
専門家に依頼するメリット
形状上のリスクを有する既存住宅の耐震補強は、専門的な知識と実務経験が欠かせません。構造設計一級建築士や耐震診断技術者といった専門家に依頼することで、安全性向上のために最適な補強方法が提案され、施工の信頼性も確保されます。
特に、形状不整による「剛心(ごうしん)」と「重心」のズレを調整するためには、建物ごとに異なる荷重と剛性バランスをシミュレーションし、計算によって補強方法を決定する必要があります。専門家が対応することで、必要最小限の補強で効果的かつ経済的な改修が実現可能です。
さらに、工事後の評価証明書や住宅性能評価書が発行されることで、建物の資産価値向上や地震保険料の割引、市場への再販時の優位性にも直結します。
このように、形状リスクのある住宅補強は、正しい知識と技術に基づいた対応が不可欠であり、専門家のサポートを受けることは安全だけでなく将来的な利益にもつながります。

まとめ
家の形状は耐震性能に大きく影響し、凹凸の少ない四角い家は力が均等に伝わりやすいため地震に強いとされています。特に、耐力壁の配置や重心と剛心のバランスが取りやすく、阪神淡路大震災や東日本大震災でもその効果が確認されています。新築時には平面計画や構造工法を慎重に選び、既存住宅では耐震診断や補強でリスクを減らすことが重要です。